もしご希望なら、この迷路をシミュレーションして、実際にActorの行動確率がどう変化するか をコードでお見せできますが、見てみますか? → お願いします。
■迷路問題 : S(Start)から出発して、G(Goal)に至る迷路(?)
■お願いした事項: Go言語で作成をお願いします。
■プログラムで何をやっているか。
評価値は、ゴールに到着した時以外、一切与えていません。
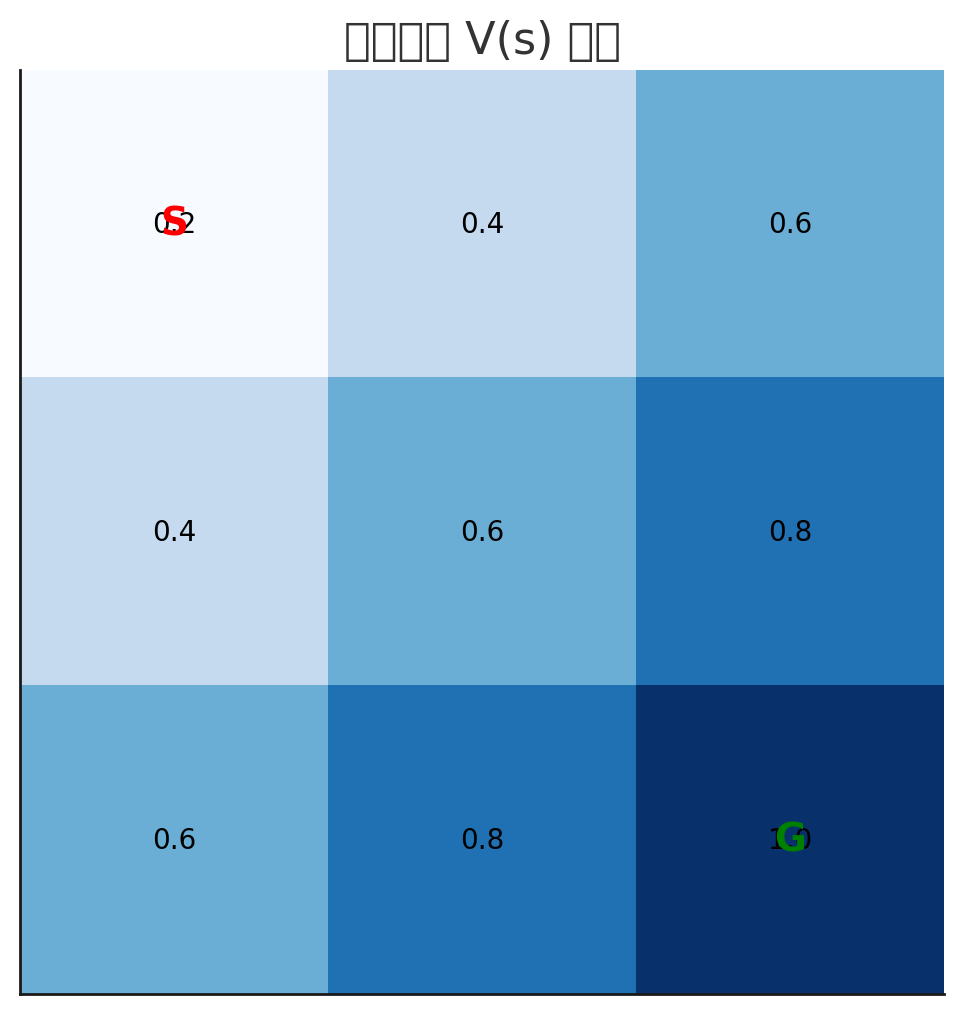
出てきたコードの各行の内容を全部質問して、コードの中に全部書き込みました。
時間はかかりましたが、ようやく分かってきました。
G:\home\ebata\actorcritic_maze3x3.go
package main
import (
"fmt"
"log"
"math"
"math/rand"
"time"
)
type State struct{ r, c int }
const (
rows, cols = 3, 3
gamma = 0.90 // 割引率
alphaA = 0.10 // Actor学習率
alphaC = 0.10 // Critic学習率
episodes = 4000 // 学習エピソード数
maxSteps = 50 // 1エピソード最大ステップ
/*
1. エピソード (episode) とは
スタート地点からゴール or 強制終了まで の一連の試行を「1エピソード」と呼びます。
このプログラムでは、S(0,0) から始めて、ゴール(G)に到着するか、maxSteps に達するまでが1エピソードです。
episodes = 4000 は、この「試行」を4000回繰り返して学習を積み重ねる、という意味です。
2. ステップ (step) とは
エージェントが「行動を1回選んで、次状態に遷移し、報酬を得る」流れを1ステップと呼びます。
maxSteps = 50 は、1エピソードの上限です。
例えば、ゴールにたどり着けなかったとしても「50ステップ経ったら強制終了」して次のエピソードに移る、という仕組みです。
*/
)
var (
start = State{0, 0}
goal = State{2, 2}
// 行動: 0=↑, 1=→, 2=↓, 3=←
dirs = []State{{-1, 0}, {0, 1}, {1, 0}, {0, -1}}
)
// 迷路外・壁チェック(今回は外枠のみ)
func valid(s State) bool {
return 0 <= s.r && s.r < rows && 0 <= s.c && s.c < cols
}
func step(s State, a int) (next State, r float64, done bool) {
next = State{s.r + dirs[a].r, s.c + dirs[a].c}
if !valid(next) {
// 迷路外は元の場所にとどまる(報酬0)
next = s
}
if next == goal {
return next, 1.0, true // ゴール報酬
}
return next, 0.0, false
}
// ソフトマックス。数値安定化のため最大値を引く
func softmax(x []float64) []float64 {
maxv := x[0]
for _, v := range x {
if v > maxv {
maxv = v
}
}
exp := make([]float64, len(x))
var sum float64
for i, v := range x {
e := math.Exp(v - maxv)
exp[i] = e
sum += e
}
for i := range exp {
exp[i] /= sum
}
return exp
}
// π(a|s) に従ってサンプル
func sample(probs []float64, rng *rand.Rand) int {
u := rng.Float64()
acc := 0.0
for i, p := range probs {
acc += p
if u <= acc {
return i
}
}
return len(probs) - 1
}
func key(s State) int { return s.r*cols + s.c } // cols=3 keyはGivenか?
func main() {
rng := rand.New(rand.NewSource(time.Now().UnixNano()))
// Critic: V(s)
V := make([]float64, rows*cols)
// Actor: θ(s,a)(各状態で4行動のスコア)
theta := make([][4]float64, rows*cols)
// 学習ループ
for ep := 0; ep < episodes; ep++ { // エピソード4000
s := start
for t := 0; t < maxSteps; t++ { // maxSteps=50
if s == goal {
break
}
// 方策 π(a|s) = softmax(θ(s,*))
k := key(s) // 状態S = (r,c)を k= r x cols + c で1次元に変換したもの
scores := theta[k][:]
/*
theta は 「各状態ごとの4つの行動に対応するスコア(パラメータ)」 を保持する配列です。
例えば状態が全部で9個(3×3迷路)なら、theta は [9][4]float64 型になります。
1次元目 = 状態インデックス k
2次元目 = 行動(↑→↓←の4つ)
scores := theta[k][:] の意味
theta[k] は、状態 k に対応する 4つの行動スコア(配列 [4]float64)です。
[:] を付けることで、それを スライス([]float64) として取り出しています。
つまり、(↑→↓←の4つ)の行動スコアを取ってくる処理です。
*/
pi := softmax(scores)
/*
ここが Actor-Critic の Actor が「方策 π」を計算する部分 です。
状態 s(インデックス k)における 行動スコア(4つ) が入っています。
例:scores = [0.5, -0.2, 1.0, 0.0]
2. softmax(scores) の処理
ソフトマックス関数は、入力ベクトルを 確率分布 に変換します。これにより、行動スコアを「各行動を選ぶ確率」に変換できます。
もし
scores = [0.5, -0.2, 1.0, 0.0]
pi := softmax(scores)
とすると:
exp(0.5) =1.65
exp(-0.2)=0.82
exp(1.0)=2.72
exp(0.0)=1.00
合計 = 1.65 + 0.82 + 2.72 + 1.00 = 6.19
したがって確率は:
π[0] = 1.65/6.19 = 0.27
π[1] = 0.82/6.19 = 0.13
π[2] = 2.72/6.19 = 0.44
π[3] = 1.00/6.19 = 0.16
となり、pi = [0.27, 0.13, 0.44, 0.16] となります。
つまり、この状態で「下(3番目の行動)」を選ぶ確率が一番高い という方策が得られる。
*/
// 行動サンプル
a := sample(pi, rng) // 「Actor が方策 π(a|s) に従って行動を選ぶ」処理
/*
もし pi = [0.1, 0.7, 0.2, 0.0] なら、
10%の確率で行動0(↑)
70%の確率で行動1(→)
20%の確率で行動2(↓)
0%の確率で行動3(←)
が選ばれることになります。
*/
// 遷移
s2, r, done := step(s, a)
/*
報酬 r は、環境に組み込まれた「設計者が定めたルール」によって与えられる数値です。
- ある行動をしたときに「良いこと」が起きれば正の報酬
- 「悪いこと」が起きれば負の報酬
- 何も特別なことがなければ0
報酬の設計は、人間(研究者・エンジニア)がタスクに合わせて 「何を良しとするか」 を決めているのです。
今回のプログラムでは、ゴール以外はすべて報酬0 に設計されています。
- ゴールに到着するまでは報酬が一切なく、ゴール時にだけ+1をもらえる
- これは「スパース報酬(Sparse Reward)」と呼ばれる典型的な強化学習の難しい設定です
- エージェントは「長い間0ばかりの報酬」を経験し、たまたまゴールに着けたときだけ「報酬1」を得る → そこから学習が始まる
ちなみに、以下のような報酬にすることも可能です。
- ゴールに近づいたら +0.1
- 壁にぶつかったら -0.1
- ゴールで +1
*/
// TD誤差 δ = r + γ V(s') - V(s)
delta := r + gamma*V[key(s2)] - V[k]
/*
Q: 行動前後の状態関数値に、報酬値(行動関数値)を混在させているように見えますが、この理解で正しいですか
まさに 「行動前後の状態価値に、報酬を加えた誤差(TD誤差)」 を計算しています。
ご指摘の「混在させているように見える」というのは正しい理解です。
V(s):行動前の状態の予測価値
r:その行動で得られた報酬(行動の良し悪しを直接反映)
γ V(s'):次の状態の予測価値(将来の報酬を考慮)
なぜ混在させるのか→これは Temporal Difference (TD) 学習 の基本です。
- 強化学習は「報酬だけ」では学習が進まない(スパース報酬だと特に)。
- そこで「次状態の価値」を推定値として使い、学習を効率化する。
- 結果として「報酬(直接的な経験)」と「状態価値(推定値)」が混在する形になります。
直感的なイメージ
- 今の予測V(s) は「この場所は0.2くらいの価値」と言っている
- でも実際に行動したら「報酬r=0」+「次の状態の価値0.4×割引0.9 = 0.36」が得られた
- すると「実際の方が良かった → 予測との差 δ=+0.16」
- この δ を Actor と Critic の両方の更新に使う
まとめ
- ご指摘の通り、報酬 r(行動の直接的な結果)と状態価値 V(将来の見込み)を混ぜている
- これは意図的で、「行動直後の経験」と「将来の予測」を組み合わせるのがTD学習の肝
- この差分 δ が、学習の駆動力(Criticの改善、Actorの方策更新)になります
*/
// Critic更新
V[k] += alphaC * delta // alphaC = 0.10 Critic学習率 Vは、状態価値関数を2次元で記載せずに、1次元にして管理している(プログラムを簡単にするため))
/*
Givenであった状態評価関数値に手を加える
*/
// Actor更新:∇θ log π(a|s) = onehot(a) - π
for i := 0; i < 4; i++ {
grad := -pi[i] // softmaxで作成された確率分布pi
if i == a { // aは4つの行動サンプルの中の1つ
grad = 1.0 - pi[i]
}
theta[k][i] += alphaA * delta * grad // alphaA = 0.10 Actor学習率
}
/*
Q: これは、行動評価関数を更新しているのだと思いますが、scoreの値(softmaxの前)と、piの値(softmaxの後)の値が混在して、混乱しています。
ここで「行動スコア(softmax前)」と「行動確率分布 π(softmax後)」が混ざって見えるのは自然な感覚です。実際には役割が違います。まずそこを分けて整理します。
1. 行動スコア(softmax前)
theta[k][i] がその正体です。
- これは 状態 s における各行動 a の「生の値(ロジット)」。
- まだ確率ではありません。
- 学習により増減して「相対的にどの行動が良いか」を表現する材料になります。
例: theta[k] = [0.1, 0.9, -0.2, 0.0] この段階ではただの4つの数。
2. 行動確率分布 π(softmax後)
- pi := softmax(scores) で計算されるもの。
- scores は theta[k][:] から取り出した 行動スコア。
- softmaxを通すことで 確率分布(和=1) になる。
- 実際に「次の行動をサンプルする」時に使われるのはこちら。
- 上の例にsoftmaxを適用すると: π=[0.23,0.52,0.11,0.14]
- つまり、Actorの「行動方策 π(a|s)」になります。
3. 混乱しやすいポイント
- 更新するのは スコア(theta)
- その更新量の計算に 確率(pi) が出てくる
- この「スコアを確率に変換して行動を選び、その確率を使ってスコアを更新する」という循環構造が混乱の原因です。
4. 整理すると
- スコア(theta[k][i]) … 内部パラメータ、学習で直接更新される
- 確率(pi[i]) … スコアをsoftmaxで正規化したもの、行動選択と勾配計算に使う
- 更新式の中で「theta を更新するが、その更新量を決めるのに pi が出てくる」ので、同じループに両方の値が登場しているだけ、ということです。
5. 「なぜ grad = onehot(a) - pi という形になるのかの説明をお願いします
はい、ここは方策勾配法の核心のひとつです。
grad = onehot(a) - pi がどこから出てくるのかを順を追って説明します。
1. 方策勾配法の基本式
Actorは「方策 π(a|s)」をパラメータ θ で表しています。
更新式の基本は次です:
∇θlogπθ(a∣s)
この勾配に TD誤差 δ を掛けて 𝜃 を更新します。
方策を softmax で定義しているので:
π(a|s) = exp(θ(s,a)) / Σ exp(θ(s,a'))
となります。これを用いると、勾配は次のように書けます:
∇θlogπθ(a∣s) = ∇θ(θ(s,a) - logΣ exp(θ(s,a')))
= ∇θ(s,a) - ∇θlogΣ exp(θ(s,a'))
= 1 - π(a|s)
対数を取ると:
log π(a|s) = θ(s,a) - log Σ exp(θ(s,a'))
4. 勾配を計算
この式を θ で微分すると:
∇θlogπθ(a∣s) = ∇θ(θ(s,a) - logΣ exp(θ(s,a')))
= ∇θ(s,a) - ∇θlogΣ exp(θ(s,a'))
= 1 - π(a|s)
もし 𝑖 ≠ 𝑎 なら:(選ばれなかった行動)なら:
∇θlogπθ(i∣s) = ∇θ(θ(s,i) - logΣ exp(θ(s,a')))
= ∇θ(s,i) - ∇θlogΣ exp(θ(s,a'))
= 0 - π(i|s)
= -π(i|s)
上記をベクトル形式で書けば:
∇θlogπθ(a∣s) = 1 - π(a|s)
∇θlogπθ(i∣s) = -π(i|s)
となり、コードの内容と一致します。
grad = onehot(a) - pi は、softmax方策の勾配
∇θ logπ(a∣s) を計算した結果そのもの
これを使うことで、
選んだ行動のスコアは強化され(確率↑)、
選ばなかった行動のスコアは抑制される(確率↓)
つまり、行動スコアを、行動スコアの確率値を乗算して、更新しつづけている、と理解すれば良いです。
*/
s = s2
if done {
break
}
}
}
// 学習結果の表示
fmt.Println("学習後の方策 π(a|s)(↑,→,↓,← の順で確率を表示)")
for r := 0; r < rows; r++ {
for c := 0; c < cols; c++ {
k := key(State{r, c})
pi := softmax(theta[k][:])
// 見やすいように丸め
fmt.Printf("s=(%d,%d): [", r, c)
for i, p := range pi {
fmt.Printf("%.2f", p)
if i < len(pi)-1 {
fmt.Print(", ")
}
}
fmt.Println("]")
}
}
// 簡易検証:スタートから1エピソード実行
fmt.Println("\nスタートから1回走らせた行動列(期待的には→や↓が増える)")
trace := simulateOnce(start, theta)
fmt.Println(trace)
}
func simulateOnce(s State, theta [][4]float64) []string {
if len(theta) != rows*cols {
log.Fatal("theta size mismatch")
}
actName := []string{"↑", "→", "↓", "←"}
var seq []string
for steps := 0; steps < maxSteps; steps++ {
if s == goal {
seq = append(seq, "G")
break
}
pi := softmax(theta[key(s)][:])
/*
状態 s に対応する 行動スコア(theta) を取り出して softmax にかける。
その結果、確率分布 π(a|s) を得る。
*/
a := argmax(pi)
/*
π の中で最も確率が高い行動を選択。
学習の検証用なので「確率的サンプル」ではなく「最大確率行動(貪欲行動)」を選んでいます。
つまり「学習済み方策がいま一番推している行動」を採用。
(注)
ここでは 学習済みの Actor(θ) だけを使って行動を選ぶ。
Critic(V) は行動選択に登場しない。
*/
seq = append(seq, actName[a])
/*
actName は []string{"↑", "→", "↓", "←"} です。
a は 0〜3 の整数(選んだ行動インデックス)。
なので actName[a] は「その行動の記号(↑→↓←)」になります。
append によって、シーケンス seq にその行動を追加していきます。
*/
ns, _, _ := step(s, a)
s = ns
/*
step() は (次状態, 報酬, 終了フラグ) を返す関数です。
ここでは戻り値のうち 次状態だけを ns に受け取り、報酬と終了フラグは _ で捨てています。
*/
}
return seq
}
func argmax(x []float64) int {
idx := 0
best := x[0]
for i := 1; i < len(x); i++ {
if x[i] > best {
best = x[i]
idx = i
}
}
return idx
}出力結果:
学習後の方策 π(a|s)(↑,→,↓,← の順で確率を表示)s=(0,0): [0.02, 0.73, 0.24, 0.02]s=(0,1): [0.01, 0.04, 0.94, 0.01]s=(0,2): [0.06, 0.06, 0.85, 0.04]s=(1,0): [0.01, 0.94, 0.03, 0.02]s=(1,1): [0.00, 0.95, 0.04, 0.01]s=(1,2): [0.00, 0.01, 0.99, 0.00]s=(2,0): [0.12, 0.65, 0.12, 0.11]s=(2,1): [0.03, 0.91, 0.04, 0.02]s=(2,2): [0.25, 0.25, 0.25, 0.25]スタートから1回走らせた行動列(期待的には→や↓が増える)[→ ↓ → ↓ G]
状態価値関数値の初期値は、今回はザックリGivenで与えられていましたが、ここは、実データの平均値とかを使う方法が一般的らしいです。