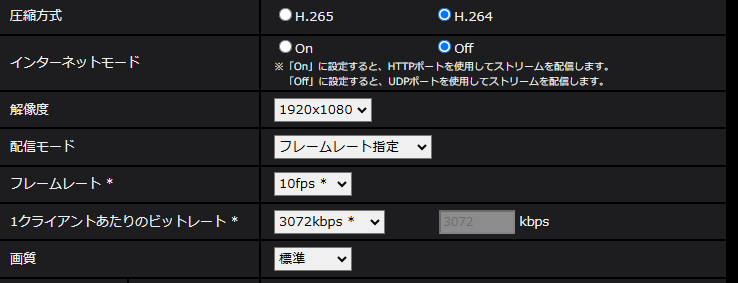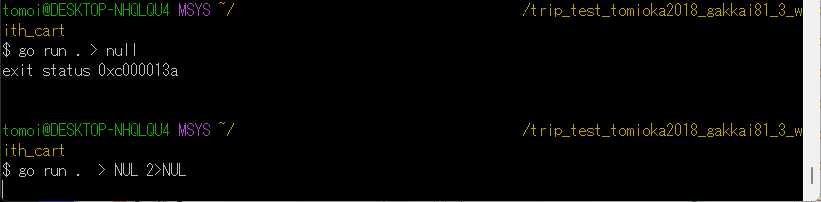GStreamer (gst-launch-1.0) と tc (Traffic Control) の "bitrate" の意味が異なるため、混乱するのは自然です。以下に、それぞれの設定が どの部分を制御しているのか を整理して説明します。
1. GStreamer (bitrate=1700) の意味
x264enc bitrate=1700
- GStreamer の
bitrate=1700は、エンコード時のビットレートを指定 しています。 - 単位は kbps(キロビット毎秒) なので、この場合 1.7 Mbps になります。
- エンコード後の映像ストリームのデータ量を決定 し、これが ネットワークに流れるデータ量の目安 になります。
- つまり、GStreamer の設定は「この映像ストリームのビットレートを 1.7 Mbps にしなさい」という指示 です。
✅ 換算
- 1700 kbps = 1.7 Mbps
- 1.7 Mbps = 約 0.212 MB/s(メガバイト毎秒)
- 計算式:
1.7 Mbps ÷ 8 = 0.212 MB/s
- 計算式:
2. tc (rate 5mbit) の意味
tc qdisc add dev eth0 root tbf rate 5mbit burst 10kb latency 50ms
tcのrate 5mbitは、ネットワークインターフェース (eth0) の最大帯域を制限する設定 です。- 単位は Mbps(メガビット毎秒) なので、この場合 5 Mbps になります。
- これは 「eth0 から送信できる最大速度を 5 Mbps に制限しなさい」という指示 です。
- つまり、GStreamer が 1.7 Mbps の映像を送信しようとしても、5 Mbps の帯域制限があるため、この範囲内なら問題なく送信できる。
✅ 換算
- 5 Mbps = 約 0.625 MB/s(メガバイト毎秒)
- 計算式:
5 Mbps ÷ 8 = 0.625 MB/s
- 計算式:
3. GStreamer bitrate=1700 と tc
rate=5mbit の関係
(1) GStreamer のビットレートが tc の制限内に収まる場合
- GStreamer (
bitrate=1700 kbps = 1.7 Mbps) tcの制限 (rate=5mbit = 5 Mbps)- 1.7 Mbps < 5 Mbps → 問題なく通信できる
- 映像ストリームのデータ量は 1.7 Mbps なので、帯域 5 Mbps では十分。
(2) GStreamer のビットレートが tc の制限を超える場合
例えば、GStreamer の bitrate=6000(6 Mbps)と設定した場合:
- 6 Mbps >
tcのrate=5mbit - 制限(5 Mbps)を超えているため、パケットロスが発生する可能性がある
- 映像が乱れたり、ストリームが停止する可能性がある
このように、GStreamer の bitrate は映像のエンコード後のデータ量、tc の rate はネットワークの最大許容量を決める ため、両者の関係を考える必要があります。
4. まとめ
| 設定 | 役割 | 値の意味 | 設定値(例) |
|---|---|---|---|
GStreamer bitrate |
映像エンコードのビットレート | 送信するストリームのデータ量 | bitrate=1700 → 1.7 Mbps |
tc
rate |
ネットワークの最大帯域制限 | インターフェースの最大通信速度 | rate=5mbit → 5 Mbps |
結論
- GStreamer の
bitrateは「どれだけのデータを送るか」 tcのrateは「送れるデータ量の上限」- GStreamer のビットレートが
tcの制限内なら問題なし(1.7 Mbps < 5 Mbps) - GStreamer のビットレートが
tcの制限を超えるとパケットロスの可能性あり(例: 6 Mbps > 5 Mbps)
つまり、現在の設定(bitrate=1700 と rate=5mbit)では 1.7 Mbps の映像を 5 Mbps の帯域内で余裕をもって送信できる ということになります。
よし、これは分かった。