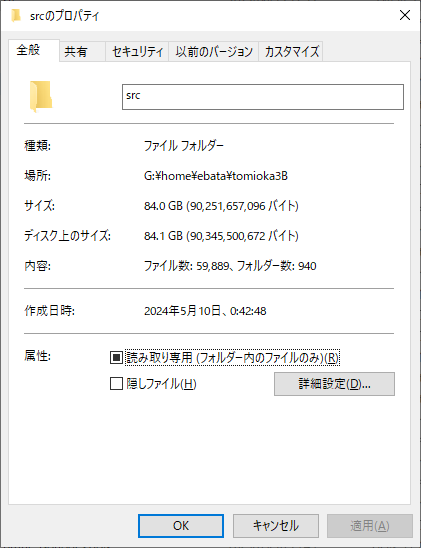https://www.kobore.net/tex/alone93/node21.html
江端さんのひとりごと
「危ない炊飯器」
江端さんのひとりごと'93
大学と大学院に在学していた時、私は京都の最北端に位置する「岩倉」と言うところに下宿していました。岩倉は緑の多い静かな町で、ちょうど比叡山のふもとに位置す る場所にあります。
岩倉は、大学から10km以上も離れているので、友人たちもよほど堅い決心をしないと、 私の下宿にやってくることが出来ません。交通の便も決して良いとは言えず、飲食店も比較的早い時間に閉まってしまうので、学生に人気のある町ではなかったようです。
しかし、私は大学院を卒業するまでの6年間、ついにここを離れることはありません でした。私の下宿は古いアパートの6畳1部屋だけしかなく、風呂、トイレ、炊事場 は共用でしたが、20部屋もあったそのアパートに住んでいたのは、わずか3人だけで、 私は自分の部屋と、両隣の2部屋を自由に使うことができました。さらに、下宿料金 が信じられないほど格安でした。なにしろ、一月で東京-京都間の新幹線の片道料金 程度でしたから。
音響関係で隣人との諍いを起こすことすら出来ないこの理想的な環境で、私は好きな 時に自由自在に部屋でやることが出来ました。大家が聞いたら真っ青になりそうなこ とでしたけど。
電気コードを部屋中に張りめぐらし、改造したコンピュータや、学校から黙って持っ てきた計測器をそこらに置いていました、トランジスタやicを使って、部屋中の灯りを赤外線リモコンで点灯させる装置や、ビデオとテレビの電源を連動させる装置など、 様々な訳の分からないものをたくさん作っていましたし、家庭用の調味料で危ない実験もしていました。
また、料理を作ることも結構好きでしたので、友人たちをわざわざ岩倉まで呼び寄せ て、鍋やスキヤキの他にも、カレーやシチューでパーティをしました。6畳に11人 が入った時には、さすがに困りましたけど。
---------------
大学院1年の初夏の頃、名古屋の両親が私の下宿やって来ることになりました。
その日両親は私の下宿に泊まっていくことになっていたので、私はとりあえず親子3 人が寝転べるように部屋を片付けて、夕食の準備を始めました。(まあ、焼肉かスキヤキだな)、と考え近くの店に行って材料とビールを買ってきて、食器の準備などを していました。
その時点で、私は大変なことに気がつきました。
「ご飯」です。
私の使っていた炊飯器は、大学の寮に入っていた時に、隣の空き部屋に無造作に転がっ ていた物ですが、ご飯を作るのには何の支障もなかったので、そのまま下宿に引っ越す時についでに頂いてきたものです。
炊飯器には何の支障もなかったのですが、炊飯器の「中身」が大問題でした。
半年前、私はその炊飯器を使ってご飯を作ったのですが、その時、ご飯が炊飯器に残っていたことを、すっかり忘れてそのまま放置してしまったのです。それから一月後、 そんなことをすっかり忘れていた私が、うっかりその蓋を開けた時!
そこには、底一面にこの世のものとも思われぬ、色とりどりの極彩色のカビ、カビ、 カビ・・・。そして、凄まじいまでの強烈な腐敗臭。
蓋を開けた次の瞬間に蓋をぴったり閉じて、呆然とした眼差しで肩で息をしていた 私でした。
(見てはならないものを見てしまった!)と強烈に後悔しましたが、しかし時すでに 遅く、それから数日の間、私は極彩色の悪夢に苦しめられることになります。
勿論、その炊飯器を、今度の粗大ごみの時にでも捨ててしまおうと、押入の奥深くに 「開かずの炊飯器」として封印したのですが、またしても、そのことを忘れてしまっていた訳です。
しかし、事態は切迫していました。
両親はもうすぐやってくるし、炊飯器をぽんと買えるお金など全くありませんでした。 しかし、材料もビールも買ってきてしまって、ここまで準備して外食するなど私のプライドと財政が許しませんでした。なにより、お酒が全くだめな父は、ご飯と言う食べ物をこよなく愛していましたから、息子としてはなんとしても、ご飯を炊きたかっ たのです。
私は決心しました。とりあえず、あの「開かずの炊飯器」の封印をといて見て、そ れから後のことは後で考えようと。
爆弾の信管を取り出すような手つきで押入から取り出した炊飯器を、6畳の部屋のど真中に静かに置き、部屋の窓、ドアを全て全開し、バイク用のフルフェイスメットにマスクと軍手で完全に武装し、来たるべき敵に備えました。
大きく息を吸い込んでから、私はかっと目を見開いて敢然と炊飯器の蓋を開けました。
しかし、そこにはあの極彩色の物体はどこにもなく、茶色の液体が溜っているだけでした。少し振ってみると粘り気はほとんどなく、単なる水溶液で、こわごわと臭いを かいでみると、刺激臭などなく、ほとんど無臭状態。
おそらく、炊飯器の中身はカビなどの細菌によって、分解の限りを尽くされ、もはや腐敗できるのものは何一つ無くなってしまったのでしょう。そして、腐敗を促していた細菌もまた、栄養源を失いこの炊飯器の中で死滅していったのです。この炊飯器の中の世界では、もはやいかなる形の変化も起こり得ず、最も安全で安定な物質になって行ったのです。
私は、この炊飯器の中身をぼんやりと見続けていました。 繁栄の限りを尽くして全滅していった細菌たち。私はこみ上げるような、悲しみと、 底知れぬ、いとおしさを感じずにはいられませんでした。
(ああ、これを虚無というのだな。ものごとが終るとは、時間が経つとは、こういう ことなんだな。)
そこには、宇宙の最終形態である、エネルギー移動が全くない「完全な宇宙の熱量死」がありました。
結局、私は『この炊飯器は完全に無害である』と裁可しました。といっても、徹底的に洗剤で洗い、漂白剤で殺菌し、さらに煮沸消毒をしてから使うことにしましたけど。
昼過ぎになって、自家用車ではるばる京都までやってきた父も母。夕食時には、久しぶりに会う息子と、親子水入らずでスキヤキをつついて、大変満足であったようです。 父が最初にご飯を口にした時、思わず引きつった私でしたが、それをなんとか無理矢理笑顔に代えて、おかわりのご飯をついでいた私でした。
---------------
そして、瞬く間に、月日が過ぎ去り、私も社会人になって2年が経過しました。父も 母も、そして私も、今なお健在です。
でも、未だに、彼らはこのことを知りません。