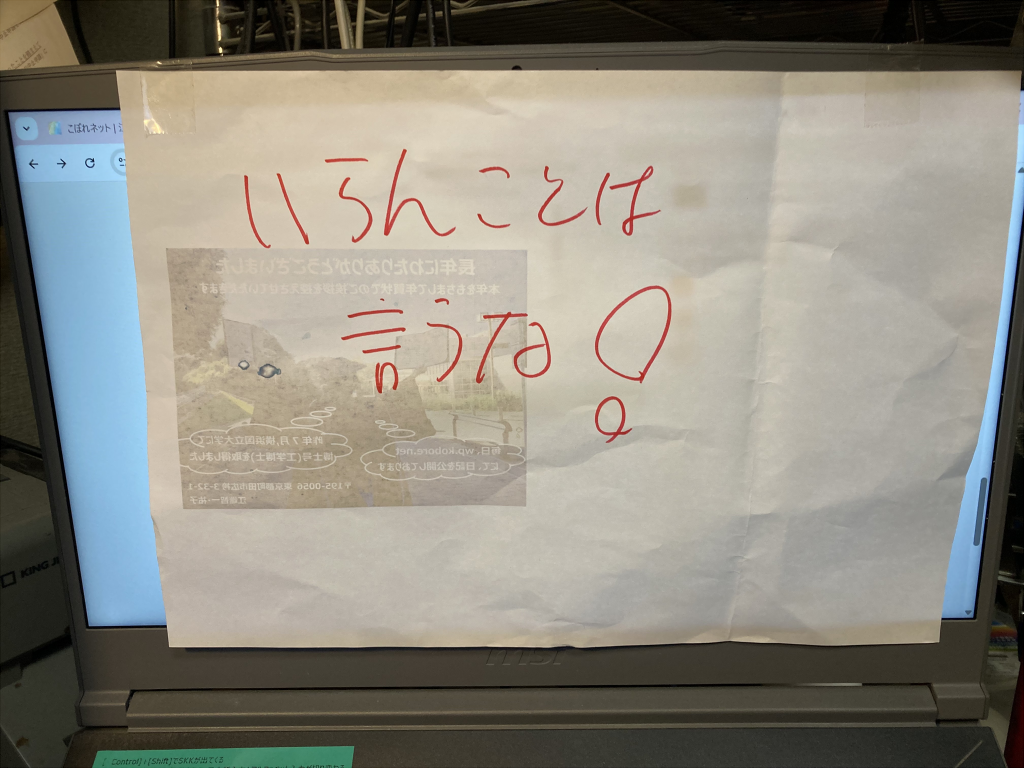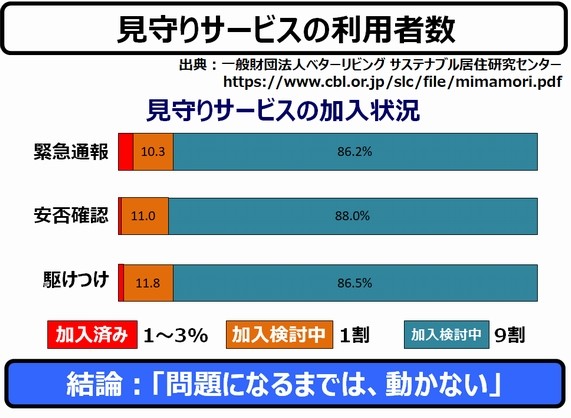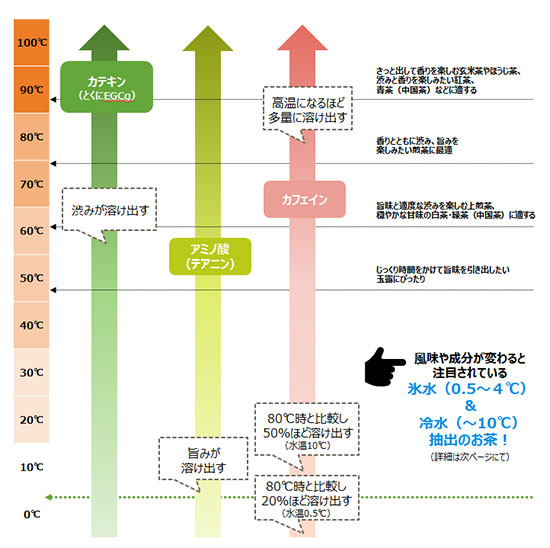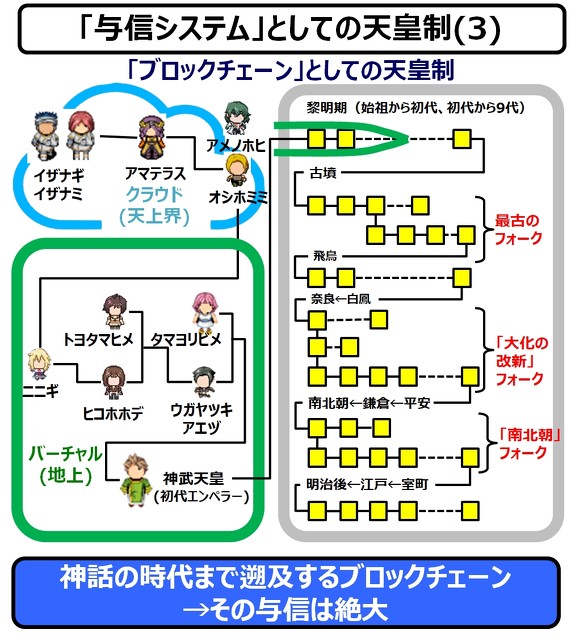年末に録画していたNHKの番組を消化していました。今回は、「未解決事件 File.06 詐欺村 国際トクリュウ事件」でした。
Today, I caught up on a recorded NHK program. It was “Unsolved Cases File.06: Scam Village? The International Tokuryu Case.”
トクリュウ ―― 「匿名・流動型犯罪グループ」。
Tokuryu ? “anonymous and fluid criminal groups.”
最初は、よくある社会派ドキュメンタリーのつもりで見始めたのですが、途中からどうにも落ち着かなくなりました。
At first, I started watching it as just another typical socially conscious documentary, but partway through, I began to feel increasingly unsettled.
―― これは単なる国際犯罪の話ではなく、国際ITシステムの運用事例ではないか?
This is not merely a story about international crime. It is a case study in the operation of a global IT system.
という感覚が、どうしても拭えなかったのです。
That sense would not leave me.
---
私はシステムエンジニアです。
I am a systems engineer.
ですから、自分の会社であっても、国際的なネットワークに基づくITシステム(物流や運輸のようなサプライチェーンだけではなく、意思決定プロセスを含めたオフィスシステムも含める)を安定運用することが、どれほど大変かは身に染みています。
Therefore, even within my own company, I know firsthand how difficult it is to operate IT systems across international networks in a stable manner, not only supply chains such as logistics and transportation, but also office systems that support decision-making processes.
言語、法制度、文化、責任分界、ネットワーク、人的ミス。どれか一つ欠けても、すぐにシステムは壊れます。
Language, legal systems, culture, boundaries of responsibility, networks, and human error, if even one of these is missing, the system quickly breaks down.
それを、"トクリュウ"はやっている。しかも、ほぼリアルタイムで、継続的に。
And yet, “Tokuryu” is doing precisely that almost in real time, and continuously.
もちろん、倫理的には論外です。しかし技術者としては、正直に言って「完成度が高すぎる」と感じてしまったのです。
Of course, ethically, it is beyond unacceptable. But as an engineer, I honestly found myself thinking that its level of completion was too high.
この違和感が、本日のコラムの起点となります。
This sense of discomfort is the starting point of today’s column.
---
最初に着手したのは、トクリュウに取り込まれる人間側(主に若者です)です。
The first thing I examined was the human side of those who are absorbed into Tokuryu (mainly young people).
なぜ若者が、こんなにも簡単に海外に連れ出されるのか ―― これは、私にかなりの衝撃を与えました。
Why are young people taken overseas so easily? This came as a considerable shock to me.
海外というのは、日本人にとって今でも"異世界"です。言葉も法律も違う。心理的障壁は、決して低くないはずです。
Foreign countries are still, for Japanese people, another world. The language is different, the laws are different. The psychological barriers should not be low.
私の時代において、私が世界中を一人で歩いてきたのは、もちろん歩きたかったからではありますが、もう一つには「プライド型のマウント」があったことは否定できません。
In my time, when I wandered the world, it was, of course, because I wanted to, but I cannot deny that there was also a form of “pride-based one-upmanship” involved.
一人で海外を歩いてきたという実績は、当時の私には、十分に友人に「マウント」が取れるくらい"美味し"かったのです。
Walking alone overseas was itself a story, something “tasty” enough for me at the time to gain a sense of superiority over others.
特に大きな課題は「言語」です。意思疎通のできない世界に行くのは、それ自体が怖いはずです。ところが、トクリュウの構成員となることを決意した彼らは行くのです ーー まるで、「怖いものは何もない」かのようです。
The problem is language. Going to a world where you cannot communicate should, in itself, be frightening. Yet they go anyway, “as if they are thinking about nothing.”
海外の旅(特に一人旅)は、トラブルの連続で、「今の私なら絶対にしない」と言い切って良いほど困難な世界でした。
Traveling abroad should have been a world of constant trouble, so complex that I can say without hesitation that I would never do it now.
トクリュウの構成員の振舞いは、曲がりなりにも世界放浪のネタで「マウント」を取ってきた私にとっては、『驚愕』の一語に尽きます。
For someone like me, who at least used world travel as a means of one-upmanship, this was nothing short of astonishing.
---
海外で自己判断をせず、責任も負わずに済む、などということは、ありえない。そんな都合のいい世界は存在する訳がない。それでも彼らは踏み込んでいく。
It is impossible to go abroad without making judgments or bearing responsibility. Such a convenient world does not exist. And yet, they step into it anyway.
このことを考える上で、私は『対象となる若者="愚か" or "無知"』というありきたりな仮説を排除しました。その程度の仮説では、このトクリュウというシステムの完成度を説明できないと考えたからです。
At this point, I discarded the commonplace hypothesis that “the young people involved are simply foolish,” because I felt that such an explanation could not account for the sophistication of the Tokuryu system.
見えてきたのは、「判断を発生させないシステム設計・構築」でした。
What came into view was a “system design and construction that does not generate decisions.”
---
トクリュウは、安全でも合法でもないシステムです。「動いているだけ」のシステムです。
Tokuryu does not claim to be safe or legal. It is simply a system in which “for now, you just move.”
このシステムの特徴は、「(1)詳しい話は"後"」「(2)決めるのは"上"」「(3)今は"準備段階"」というように、決断点が存在しないこともあります。
I saw the terror of this system in the absence of decision points, expressed through phrases like “the details come later,” “the decision is made by those above,” and “this is just the preparation stage.”
人は、決断しなければ責任を感じません。責任を感じなければ、心理的障壁は作動しません。
If people do not make decisions, they do not feel responsibility. And if they do not feel responsibility, psychological barriers do not activate.
海外への進出とは、どんな日本人にとっても、本来「ここから先は自己責任だ」という巨大な警告装置であるはずなのに、トクリュウは、それを母国語のサポート"だけ"で巧みに隠蔽します。
For Japanese people, being abroad should inherently be a strong warning sign: “From here on, you are responsible for yourself,” yet Tokuryu skillfully conceals this through support in the native language.
「日本語の指示」「日本人同士の関係」「現地社会との非接触」。こうして海外への進出は、異世界転生ではなく「判断がまだ確定しない猶予空間」に変換されることになります。
Japanese-language instructions. Relationships among Japanese people. Non-contact with local society. In this way, overseas locations are transformed from another world into a “grace period space where decisions are not yet finalized.”
---
では、なぜ、このシステムに取り込まれるのか。
So why do they get absorbed into this system?
貧困や学力の問題は主要な要因ではありますが、このシステムの構成員になるには、もっと厄介で、現代的な特性があります。
Poverty and academic ability are significant factors, but becoming a member of this system requires more troublesome and distinctly modern traits.
彼らに共通していそうなのは、「自己判断への不信」です。
What they seem to share is a “distrust of their own judgment.”
『自分で考えて選んだ結果、報われなかった』『努力したのに、状況は良くならなかった』『判断すること自体が、リスク』と、強化学習をしてしまった。
They thought and chose for themselves, yet were not rewarded. They made efforts, but their situation did not improve. They learned that making judgments itself is a risk.
さらに、ここに「自己責任」という言葉が重なる。『失敗はすべて自分のせい』『文句を言うのは甘え』
On top of this, there is the phrase “self-responsibility.” All failures are your own fault. Complaining is a weakness.
こうした価値観を強く内面化した人ほど、「決めるのは上」という言葉に、猛烈な憧れと、強烈な解放感を覚えるのだと思います。
The more strongly someone internalizes these values, the more intense their sense of liberation is when they hear the words, “The decision is made by those above.”
ただ、この「決めるのは上」というのは、どこの世界でも同じで、私ですら、決定権を上司に委ねることで、責任回避をしているという自覚があります。
That said, the idea that “decisions are made by those above” is universal, and even I know I avoid responsibility by entrusting decisions to my superiors.
---
一方、彼らは「他者承認」を強く求めているわけではないようです。欲しているのは「役割」です。
However, they are not vigorously seeking approval. What they desire seems to be a “role.”
「名前のない仕事」「代替可能なポジション」であったとしても、「自分は今、機能している」という感覚が必要なのだと思います。
Nameless work. Replaceable positions. Even so, they need the feeling that “I am functioning right now.”
さらに彼らは、「将来を考えない」ではないように見えまうす。将来は考えているのですが、考えることによって、「考えるほど絶望が具体化すること」を忌避しているだけです。これは誰にでも(私にも)あることですが ――
Furthermore, they do not so much “avoid thinking about the future” as they avoid thinking because the more they think, the more concretely despair takes shape.
トクリュウシステムは、ここに完璧に噛み合っている
The Tokuryu system fits perfectly into this.
「短期」「今回限り」「今だけ」―― つまり、トクリュウシステムは、永続運用という概念が1mmもなく、はっきり言って、使い捨てのディスポーザブルVM(Virtual Machine)とも言えるでしょう。
Short-term. One-time only. Just for now, in other words, there is not even a millimeter of the concept of long-term operation, and frankly, it could be called a disposable VM (Virtual Machine).
---
さらに言えば、トクリュウ構成員になって海外に進出する彼らは「"善悪"で世界を俯瞰する視点がない」。
Moreover, they do not view the world in terms of good and evil.
「マニュアル通り」「指示通り」「ルール通り」。その延長線上に、たまたま"犯罪"があっただけです。
They do not believe they have the authority to judge whether something is illegal. They follow the manual, the instructions, the rules, and, along the way, there just happened to be a crime.
ですので、犯罪の自覚が恐ろしく乏しい ―― というか、はっきり言って「ない」ように振る舞っている。
As a result, their awareness of committing a crime is astonishingly weak or relatively nonexistent.
ここには、「自分はどうなってもいい」という自己破壊願望も見えます。破滅を想像できないのではなく、破滅がすでに想定内に入っているかのようです。
There also appears to be a self-destructive wish somewhere inside them: “It’s fine if I break.” It is not that they cannot imagine ruin; it is as if ruin is already within their expectations.
---
では、このシステムはなぜ運用できるのか。答えは単純です。「継続を必要としないから」です。
So why can this system operate? The answer is simple: because it does not require equilibrium.
企業は人材を育てます。国家は国民を守ります。小さなITサービスですら、継続的利用を前提にしています。
Companies develop human resources. States protect their citizens. IT services assume continued use.
トクリュウのシステムは違う。「一人一回」「短期」「消耗前提」であり「ユーザー満足度」も「信頼残高」も、存在しない。
Tokuryu is different. One person, one time. Short-term. Premised on consumption. There is no user satisfaction, no reservoir of trust.
壊れるのは"人間"であって、"システム"ではない。
What breaks is the human being, not the system.
---
私は、長いこと、このトクリュウシステムを維持している燃料やは「暴力」だと思っていました(つまり暴力による構成員の支配。まあ、「奴隷制度」ですね)。
I had thought that the gasoline sustaining the Tokuryu system was "violence" (that is, controlling members through violence, essentially a form of slavery).
これは確かに存在しますが、どうやら主因ではないようなのです。
This certainly exists, but it does not seem to be the primary cause.
暴力は最後の保険程度の扱いのようです。暴力というのは、行使されなくても、「ある」と知っているだけで機能するものですから。
Violence appears to be treated as a last-resort insurance. Violence functions simply by being known to exist, even if it is never exercised.
これは、以前からお話してきた、ミッシェル・フーコーの『監獄の誕生』に登場してくる「パノプティコン」と同じです。
This is the same as the “Panopticon” that appears in Michel Foucault’s *Discipline and Punish*, which I have discussed before.
---
番組を見終えた後、「これは異常な犯罪組織の話ではない」と考えました。
After finishing the program, I thought, "This is not a story about an abnormal criminal organization."
これは、「社会が内側に持っている欲望を、倫理と法を外して極限まで純化」した、超高精度システムと把握しました。
I saw it as a hyper-precision system that takes the desires society holds within itself and purifies them to the extreme by stripping away ethics and law.
「考えたくない」「判断したくない」「責任を負いたくない」。そもそも、私自身、日々そう思っています。
I don’t want to think. I don’t want to judge. I don’t want to bear responsibility. In fact, I myself feel this way every day.
面倒な確定申告、山のような骨折手術の保険金請求書類、社内の論文を通すための稟議、物品購入の申請や棚卸しなどなど、本当に生きていることは、うっとうしいことだらけです。
Tedious tax filings, piles of insurance claim documents for fracture surgeries, internal approval processes to get papers accepted, applications for purchasing goods, and inventory checks. Life is truly full of irritations.
私が作っているITシステムは、その欲望を安全な範囲で実現する装置ですが、トクリュウは、その制限をすべて外したシステムです。倫理的には完全に破綻しているものの、技術的には見事としか言いようがありません。
The IT systems I build are devices that realize those desires within safe limits, but Tokuryu is a system that removes all such constraints. Ethically, it is completely bankrupt, yet technically, it can only be described as brilliant.
私はITエンジニアとして、トクリュウシステムに強烈な恐怖を覚えました。
As an IT engineer, I felt an intense fear of Tokuryu.
---
トクリュウは突然変異ではありません。社会の欲望を、最も残酷な形で可視化した存在です。
Tokuryu is not a mutation. It is an entity that visualizes society’s desires in their most cruel form.
逃げないで、正面から座視すれば ――
Let us not look away, but face it head-on.
これは「向こう側」の話ではなく、「こちら側のロジックで生み出されたシステムそのもの」ということが分かるはずです。
That is not a story from “the other side”; it is a system born entirely from the logic on this side.
---
我が国においては、自己の能力や自己肯定感を低く見積もり設定することは、ある種の「美徳」として扱われてきました。
In our country, estimating one’s own abilities conservatively and keeping self-esteem low have long been treated as a kind of social “virtue.”
一方で、SNS上で見られる「イケている自分を他人に見せる」「幸せな私をアピールする」といった振る舞いは、この「美徳」に対するリバウンド的行為だと、私は考えています。
By contrast, behaviors often seen on social media, such as “showing others how cool I am” or “appealing how happy my life is,” strike me as rebound reactions against this so-called virtue.
SNSは、自分の能力や状態を“切り取って”提示する、プレゼンテーション装置としては極めて優れているからです。
This is because social media functions exceptionally well as a presentation device that allows people to selectively “cut out” and display their abilities or personal conditions.
そして、トクリュウのシステムは、まさにこの点に付け込んでいます。
And it is precisely this point that the Tokuryu system exploits.
トクリュウは、「自己肯定感を低く設定する」という本来は社会的に称揚されてきた「美徳」を、最悪の形で反転させ、犯罪行為へと変換することで
Tokuryu takes what has traditionally been praised as a social “virtue”?the act of setting one’s self-esteem low and inverts it in the worst possible way, transforming it into criminal behavior
――人間を使い潰し、人間を社会的または物理的な自死に追い込む、最低にして最悪のシステムなのです。
consuming people until they are broken, and driving them into social or even physical self-destruction, making it the lowest and most reprehensible system imaginable.