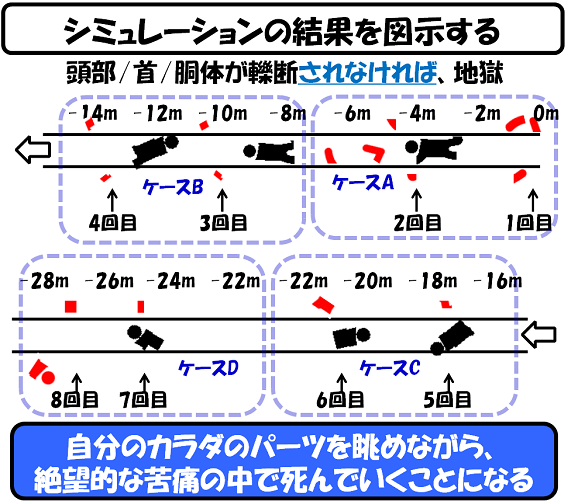『Windowsの最初の認証画面が出てくるまでの時間が非常に長いマシンがあります。別のマシンは数秒から十数秒でログイン画面がでてきます。この理由と対策方法を教えて下さい』
'There are some machines where it takes a very long time for the initial Windows authentication screen to appear. The login screen appears on other machines in a few seconds to a dozen seconds. Please tell me the reason for this and how to fix it.'
とChatGPTに質問したところ、色々対策を教えてくれました。
I asked ChatGPT this question, and it told me various measures.
Windowsの最初の認証画面(PINを入力する画面)が出てくるまでの時間が非常に長いマシンがあります(別のマシンは数秒から十数秒でログイン画面がでてきます)。この理由と対策方法を教えて下さい。
しかし、システム構成の変更にに関わる部分をいじると、高い確率で、逆に状況を悪くしたり、下手するとPCが動かなくなったりします。
However, suppose I fiddle with the parts related to changing the system configuration. In that case, there is a high probability that I will worsen the situation, or if I am not careful, my PC may stop working.
私がシステムを壊すのは、ほぼ100%、『ちょっとした改良』を施そうとした時です。
I break the system almost 100% when I try to make 'minor improvements.'
『ログイン画面の設定を変えたら、PCにアクセスできなくなった』
'I changed the login screen settings, and now I can't access my PC,'
などの他に、
and the others are
- 『ネットワーク設定を少し最適化しようとしたら、全く通信できなくなった』
- 『ブートオプションを少し調整したら、OSが起動しなくなった』
- 『電源管理設定を変更したら、スリープから復帰しなくなった』
- 『ストレージのアクセス速度を上げようとしたら、データが飛んだ』
- 『メモリの動作クロックを少し上げたら、起動しなくなった』
- 『BIOSの設定を最適化しようとしたら、画面が真っ黒になった』
- 『Windowsのレジストリを少し変更したら、ログインすらできなくなった』
- 『ドライバを最新版に更新したら、デバイスが一切認識されなくなった』
- 『仮想メモリ設定を微調整したら、ブルースクリーンが頻発するようになった』
- 『セキュリティ設定を強化したら、管理者権限での操作が一切できなくなった』
- 'I tried to optimize my network settings a little, but I couldn't connect at all.
- 'I adjusted the boot options slightly, but the OS wouldn't start.
- 'I changed the power management settings, but it wouldn't wake up from sleep.
- 'I tried to increase the storage access speed, but my data disappeared.
- 'I slightly increased the memory operating clock, but it wouldn't start up.
- 'I tried to optimize the BIOS settings, but the screen went completely black.
- 'After making a few changes to the Windows registry, I couldn't even log in anymore.'
- 'After updating the drivers to the latest version, my device stopped being recognized.'
- 'After minor adjustments to the virtual memory settings, I started getting frequent blue screens.s.'
- 'After strengthening the security settings, I couldn't do anything with administrator privileges.e.'
などがあります。
19歳の時からPCを使い続けている私ですら、このザマです。
Even I, who have been using a PC since I was 19, am like this.
『PCの設定変更が、怖くて仕方がない』という思いは、PCを使用してきた時間とは関係ありません。
The thought that 'changing the PC settings is too scary' has nothing to do with how long you have used a PC.
そしてPCには、そのPCの所有者の重要な業務情報やシステム(プログラム)が満載です。
A PC contains essential business information and systems (programs) for its owner.
私たちは、PCの中身を人質に取られながら、毎日をビクビクしながら生きているようなものです。
We live in fear daily, with our PCs holding our data hostage.
-----
で、今、あの遅いログイン画面のPCに手を加えるかどうか悩んでいます。
So now I'm wondering whether or not to modify the PC with the slow login screen.
直せるかもしれませんが、逆にもっと悪くなるかもしれません。最悪、OSが立ち上がらなくなるかもしれません。
It might be possible to fix it, but it might also worsen things. In the worst-case scenario, it might prevent the OS from starting up.
大抵の場合、私は、この結論に達します。
In most cases, I reach this conclusion.
「とりあえず、このまま使おう」
“Let's just keep using it as it is.”
と。
そして私は、いつものように、電源ボタンを押して、PCの前で祈りながら、ログイン画面が現れるまでの「永遠にも感じる時間」を待っています。
As usual, I press the power button and wait until the login screen appears, praying in front of the PC.
-----
ところが、以前、この「永遠にも感じる時間」を待ち続けた結果、数ヶ月後に、HDDがクラッシュして、業者にHDDの復旧依頼をしなければならなくなったことがあります。
However, once before, after waiting for this “time that feels like an eternity,” the HDD crashed a few months later, and I had to ask a company to recover it.
総額11万円でした。
The total amount was 110,000 yen.
PC本体(中古)が3台を購入できるお金を、自腹を切って払いました。救済できたのはHDDの中身だけで、PC本体を元に戻すことはできませんでした。
I paid out of my pocket to buy three used PCs. I was only able to rescue the contents of the HDD, and I was unable to restore the PCs to their original state.
「ただ祈っていればいい」というものでもないのです。
It's not as simple as “just praying”.
-----
ちなみに、なるべく物事を変えず、現状維持を原則とする考え方を「保守」と呼びます。
Incidentally, the idea of maintaining the status quo by not changing things as much as possible is called “conservative.”
これに対し、リスクを承知で新しい試みや考え方を積極的に取り入れ、変化を推進する考え方を「リベラル(革新)」(場合によっては「ラディカル」)と呼びます。
In contrast, the idea of promoting change by actively embracing new ideas and approaches, even if they involve risk, is called “liberal” (or, in some cases, “radical”).
人間は年齢を重ねるにつれ、「リベラル(革新)」から「保守」へと立場を変えていきます。
People change their stance from “innovation” to “conservation” as they age.
その理由は、上記のPC設定の事例だけで、十分にご理解頂けると思います。
The above example of PC settings is enough to understand the reason.
私、現状を1mmも変えないまま、安全で平和な死を迎えたいだけの、バリバリの保守です(と自負しています)が、ちょっと厳しいなぁ、と思っています、