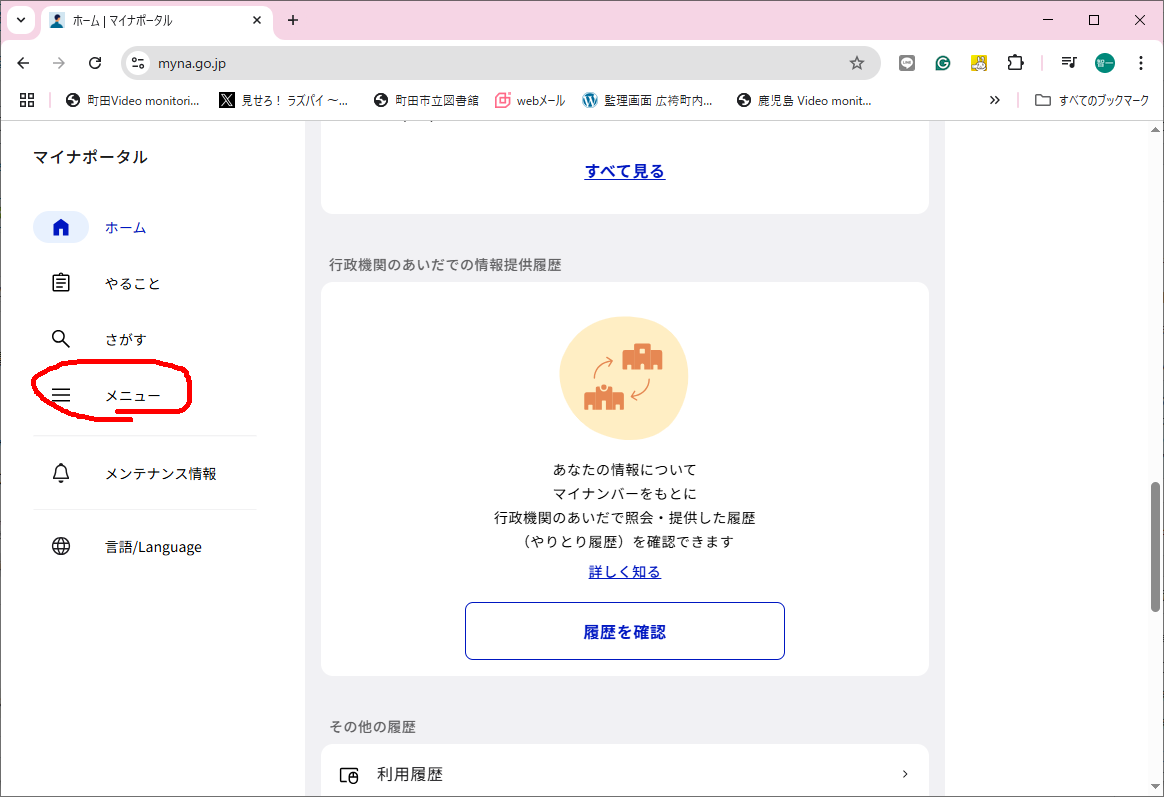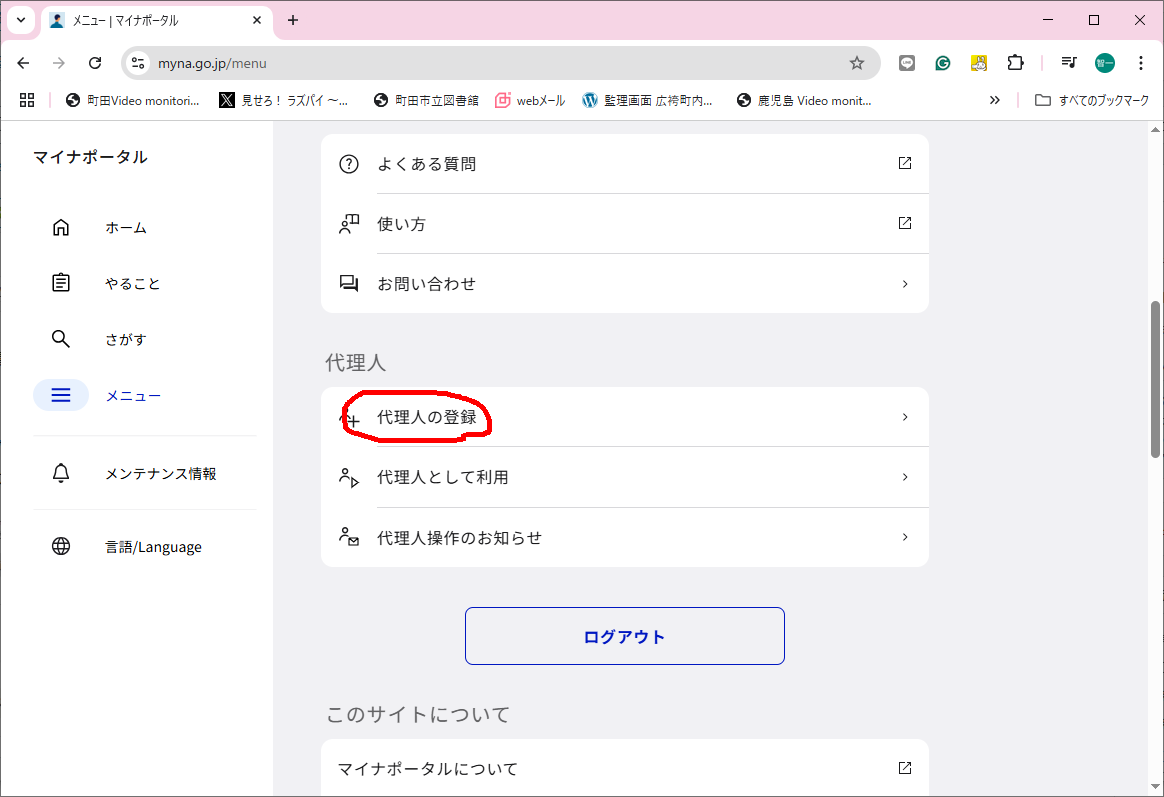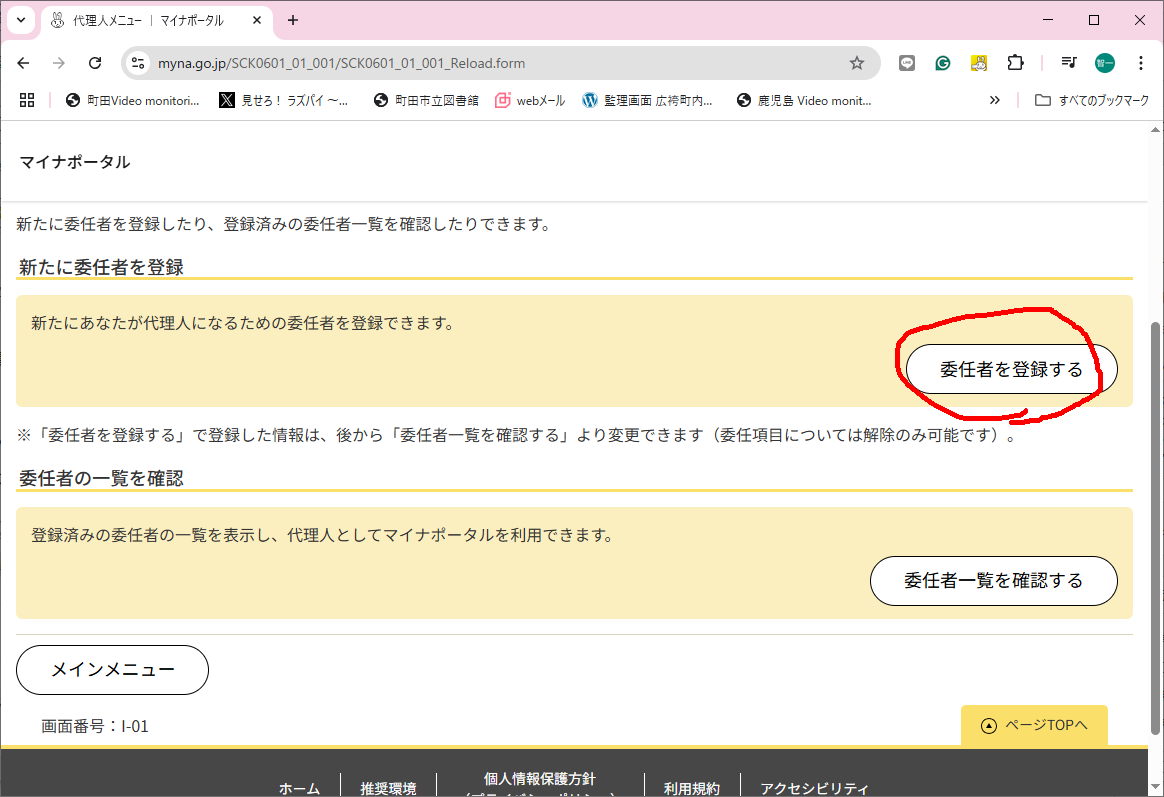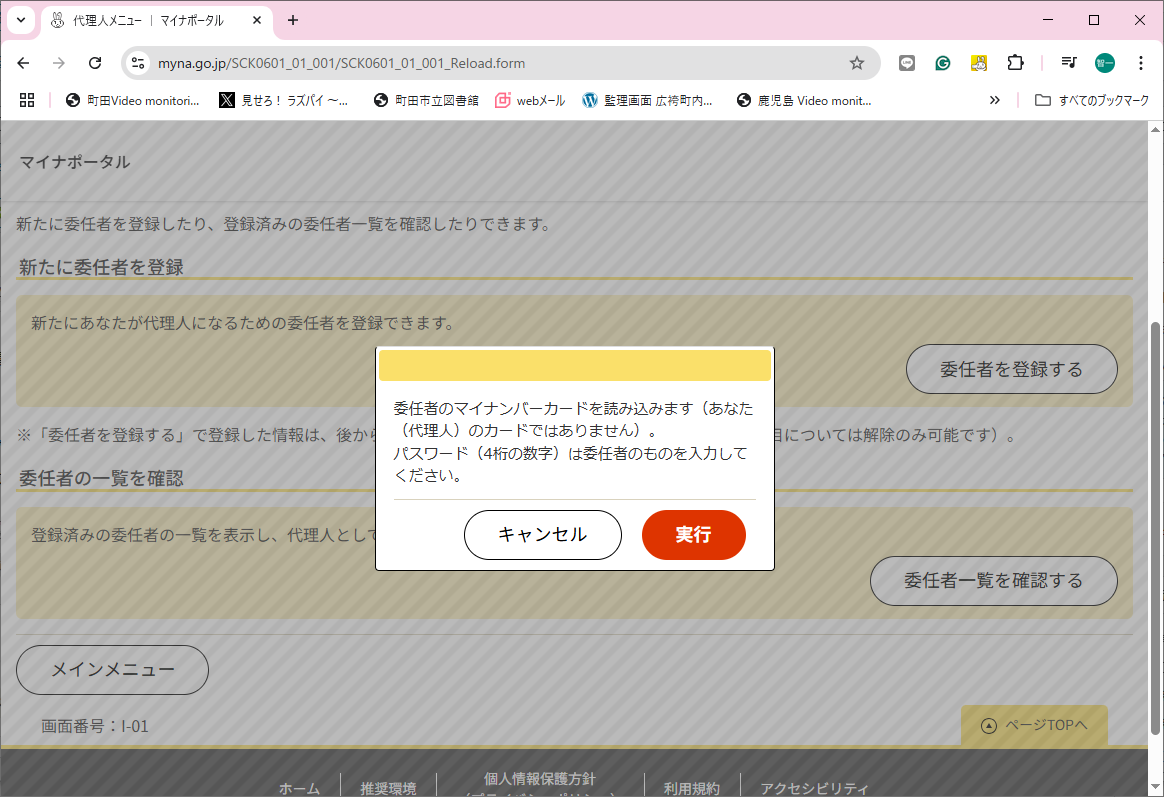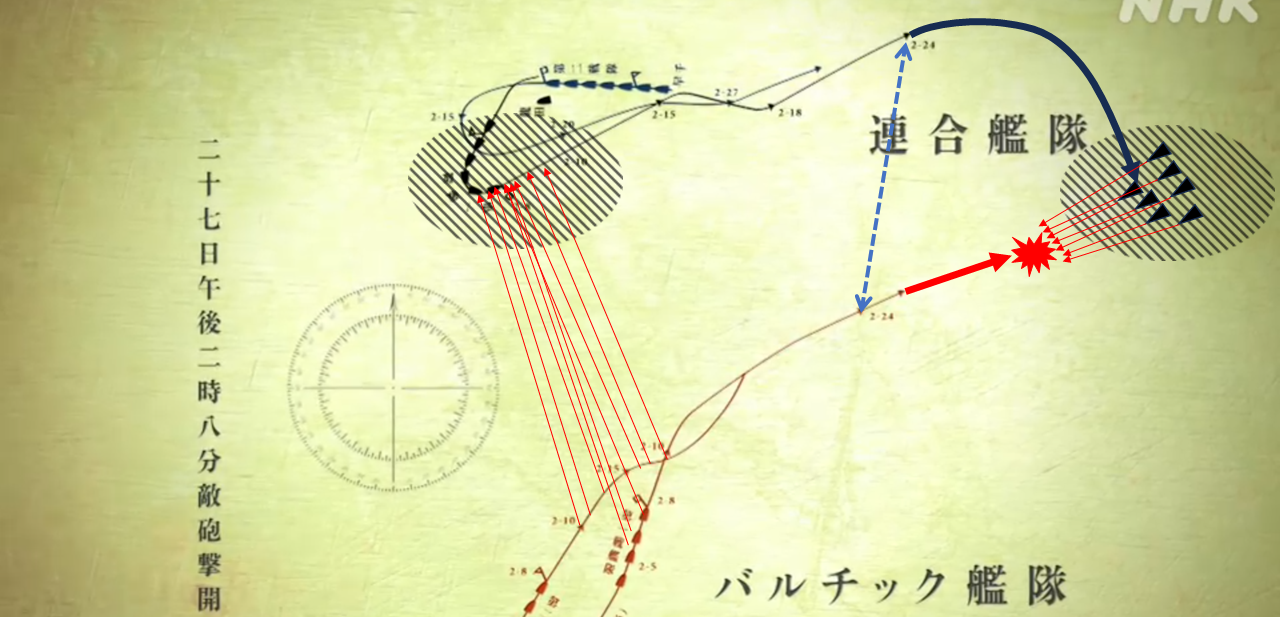「その着せ替え人形は恋をする」を読了して、コスプレという文化と技術とコスプレに傾倒する人たちの熱意とかを知ることができました。このようにコミックによって、サブカルそのものを理解できなくても、サブカルを『分かったような気にはなれる』と思いました。
サブカルに限らず、このような表現文化に関するマンガ、その他のメディアについて、ピックアックして頂き、その文化と技術と傾倒する人たちの熱意について、一覧で纒めて頂きたいです。
承知しました。以下に、先ほどの表現文化系に加えて「スポーツ」を描いたマンガを含めた一覧をアップデートしました。野球・サッカーはそれぞれ1作品のみに絞り、あまり知られていない競技(相撲・アーチェリー・スケートなど)を中心にピックアップしています。
表現文化・スポーツを描いたマンガ・メディア一覧
(文化・技術・情熱に注目)
| 作品名 | 扱っている文化/競技 | 技術的要素 | 登場人物たちの熱意・姿勢 |
|---|---|---|---|
| その着せ替え人形は恋をする | コスプレ、衣装制作 | 裁縫、メイク、造形、ウィッグ | 創作を通じた自分らしさの追求と他者尊重 |
| アクタージュ act-age | 演技、舞台・映画 | 感情表現、演技法、舞台理解 | 自己内面と演技を繋げる研ぎ澄まされた集中 |
| 映像研には手を出すな! | アニメ制作 | 絵コンテ、演出設計、世界観構築 | 想像力を具現化することへの純粋な渇望 |
| 重版出来! | 出版・編集 | 取材、企画力、マンガ制作進行 | マンガという文化を世に届ける使命感 |
| げんしけん | オタク文化全般 | 同人誌、イベント、考察 | サブカルに対する深い知識と共有の喜び |
| バクマン。 | マンガ制作 | ネーム、作画、プロ意識 | 少年の夢を現実にするための試行錯誤と覚悟 |
| ちはやふる | 競技かるた | 和歌暗記、反射、心理戦 | 伝統文化を「勝負」に昇華させる集中力 |
| ランウェイで笑って | モデル・服飾 | ファッション構成、表現力 | 身体的ハードルを越える努力と夢への執念 |
| ボールルームへようこそ | 社交ダンス | ステップ技術、ペアの呼吸、審査基準 | 表現と競技の融合を極める覚悟 |
| 火ノ丸相撲 | 相撲 | 組み手、体重コントロール、精神修行 | 小兵が巨漢に挑む意志と日本文化の継承 |
| 弓道士魂 弓玄(きゅうげん) | 弓道 | 射法八節、集中、姿勢の美しさ | 無心の精神と精度への執念 |
| スピナマラダ! | アイスホッケー | スケート技術、パス、戦術 | 東北を舞台にした熱血かつ泥臭い成長劇 |
| ノーコン・キッド | 卓球 | サーブ、ラリー、台上技術 | 地味な競技に魂を燃やす高校生たちの青春 |
| BAMBOO BLADE | 剣道 | 構え、打突、間合い | チームとの絆と勝利への葛藤 |
| あさひなぐ | 薙刀 | 構え、打突、礼節 | 女子ならではの精神的・技術的成長物語 |
| 群青にサイレン | 野球 | バッテリー、心理戦 | 心の葛藤を抱えながらも頂点を目指す兄弟 |
| DAYS | サッカー | ドリブル、連携、気持ち | 才能よりも“努力”で這い上がる物語 |
| 銀盤カレイドスコープ | フィギュアスケート | ジャンプ、表現力、演技構成点 | 表現と技術の両立に悩む選手の成長譚 |
| ツルモク独身寮 | 家具職人 | 木工加工、設計、美的センス | 若者たちの手仕事への矜持と熱意(番外的だが技術職マンガとして) |
ご覧のとおり、スポーツといっても「競技」だけでなく、「表現」や「精神性」が求められるものが多く、文化と地続きです。相撲や弓道、薙刀のような日本伝統の身体文化にも熱い想いが描かれています。
今回の私の質問の意図は、「サブカルであれマイナーなスポーツであれ、それを知ろうという行動を起こすことなく、批判しているヤツは『バカ』と断言して良い」、ということです。