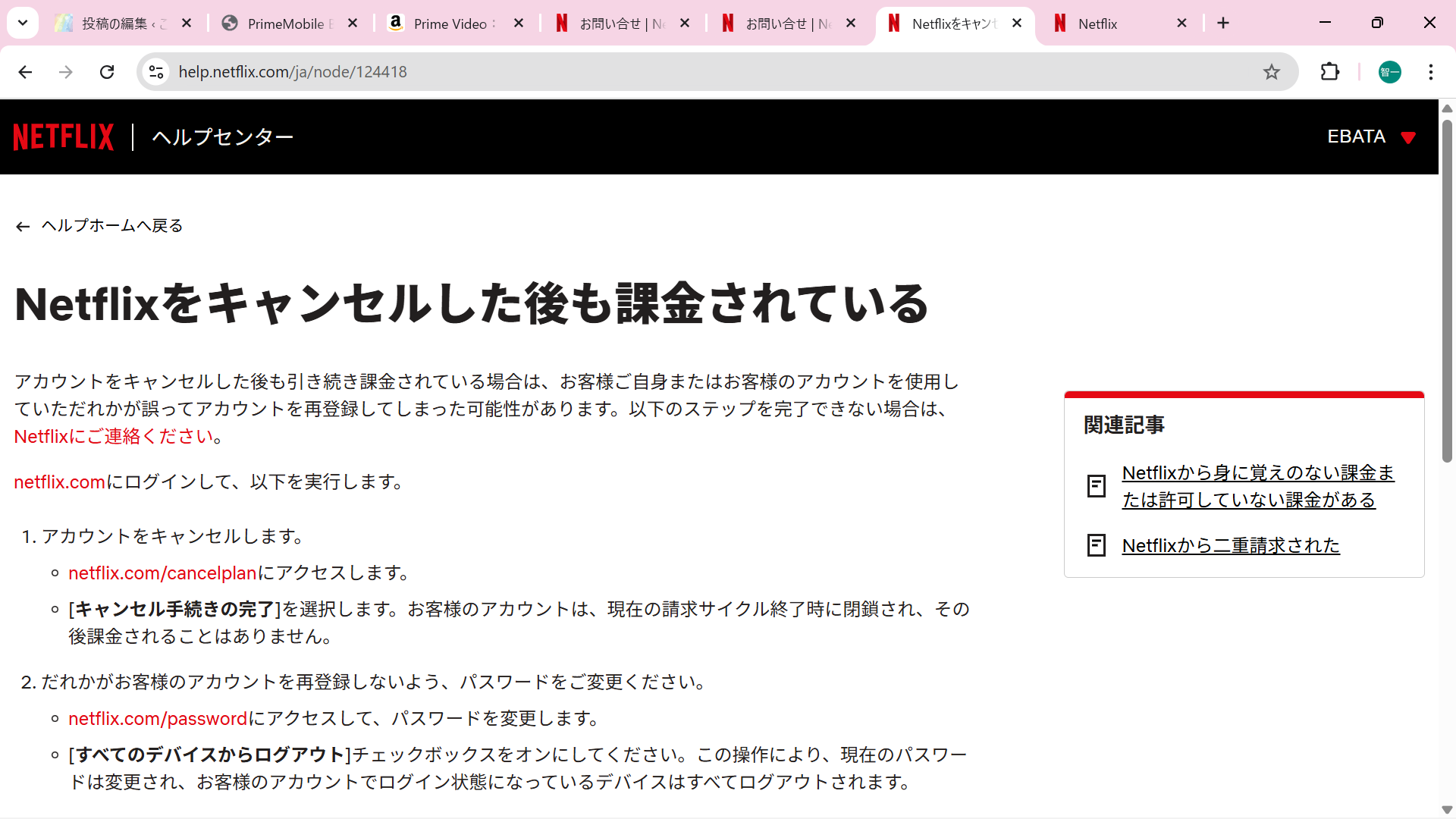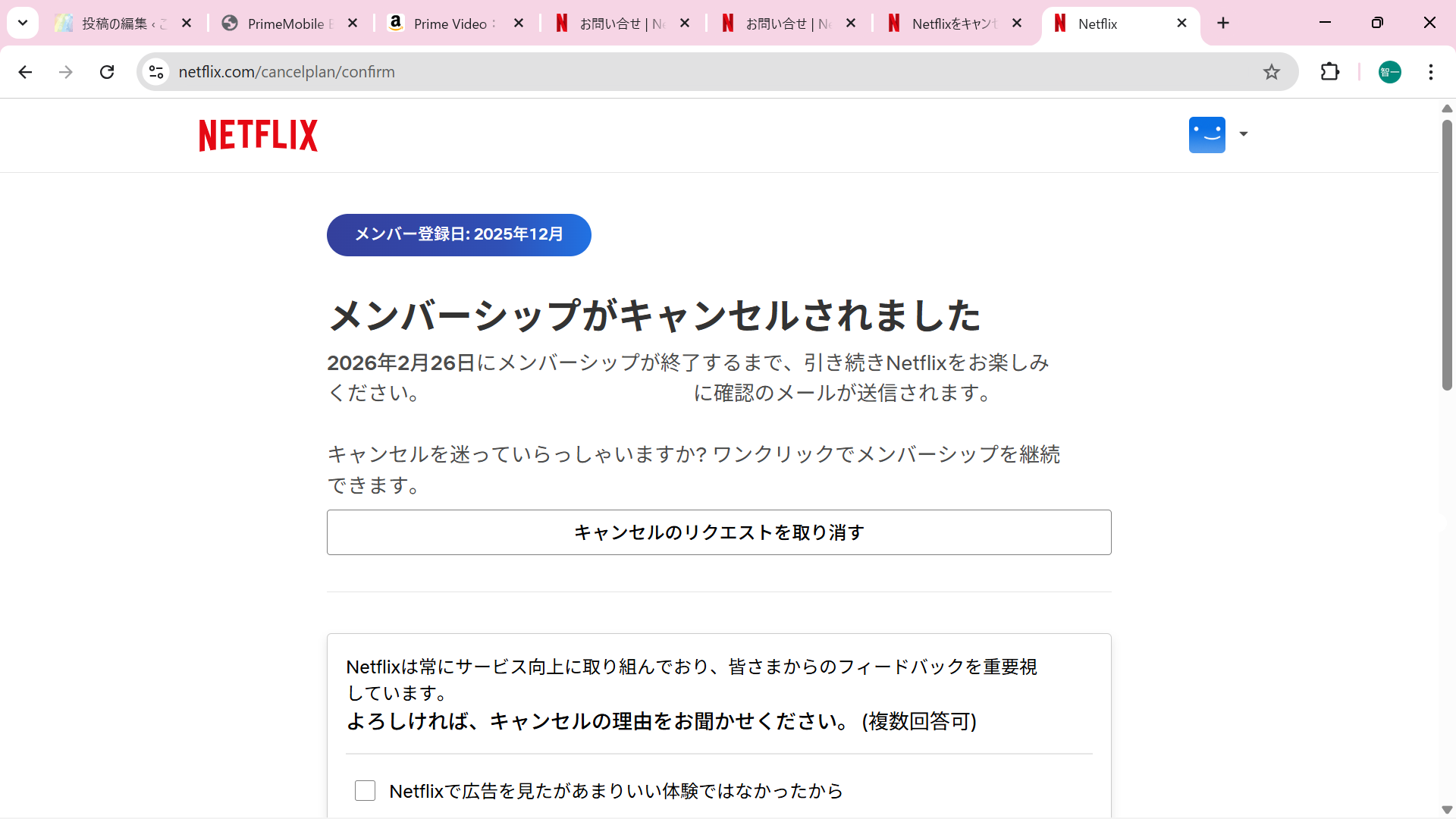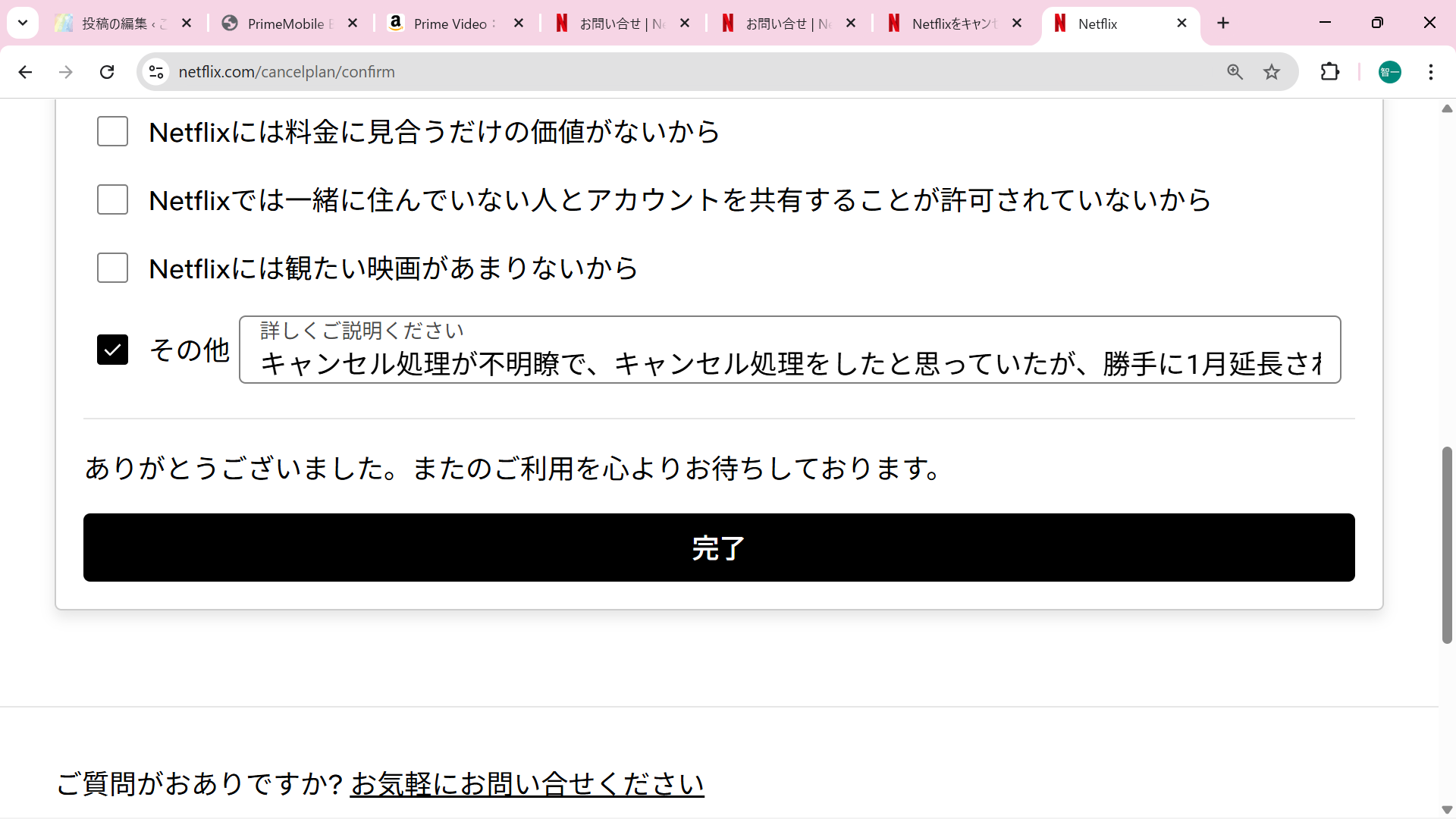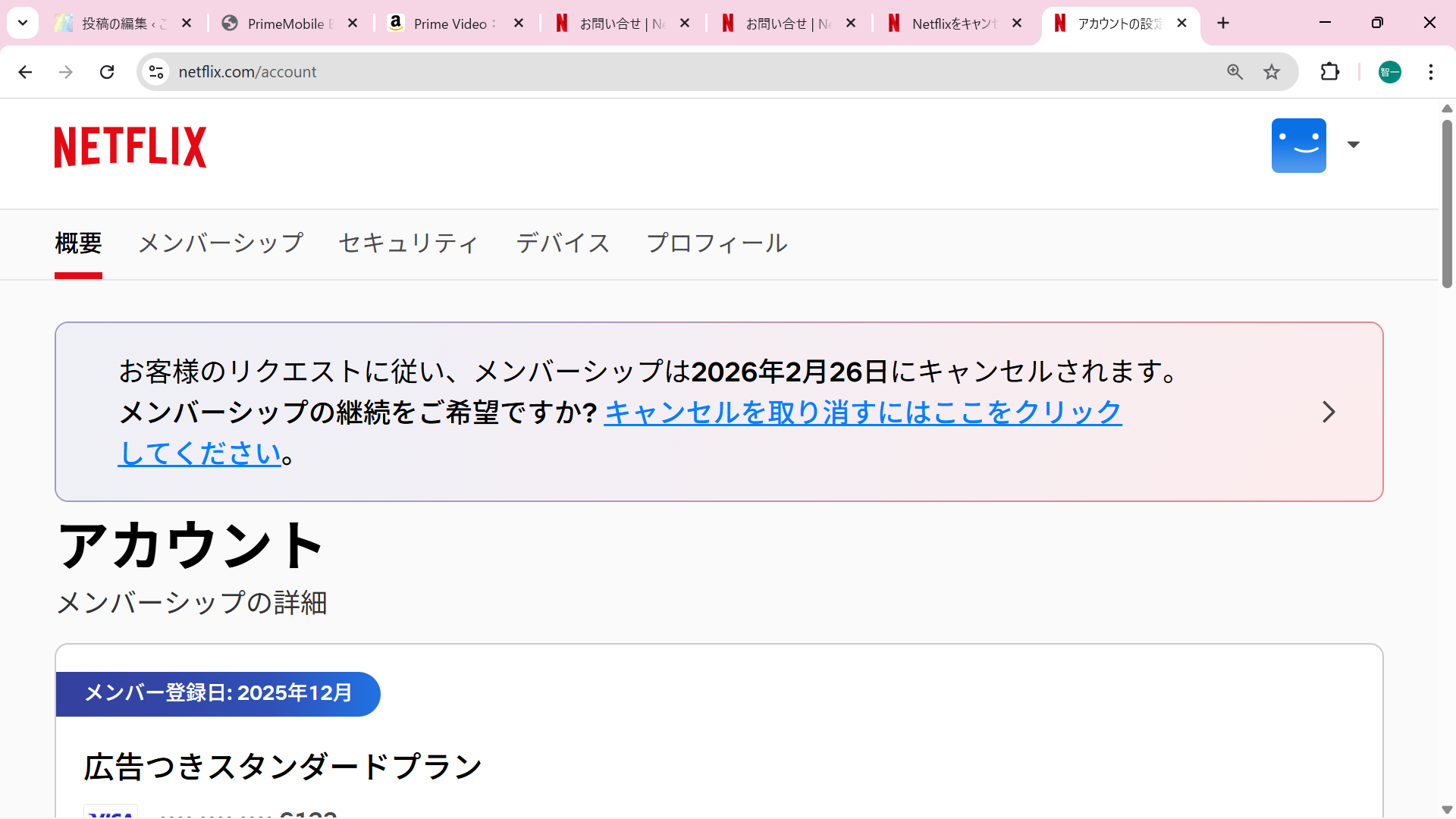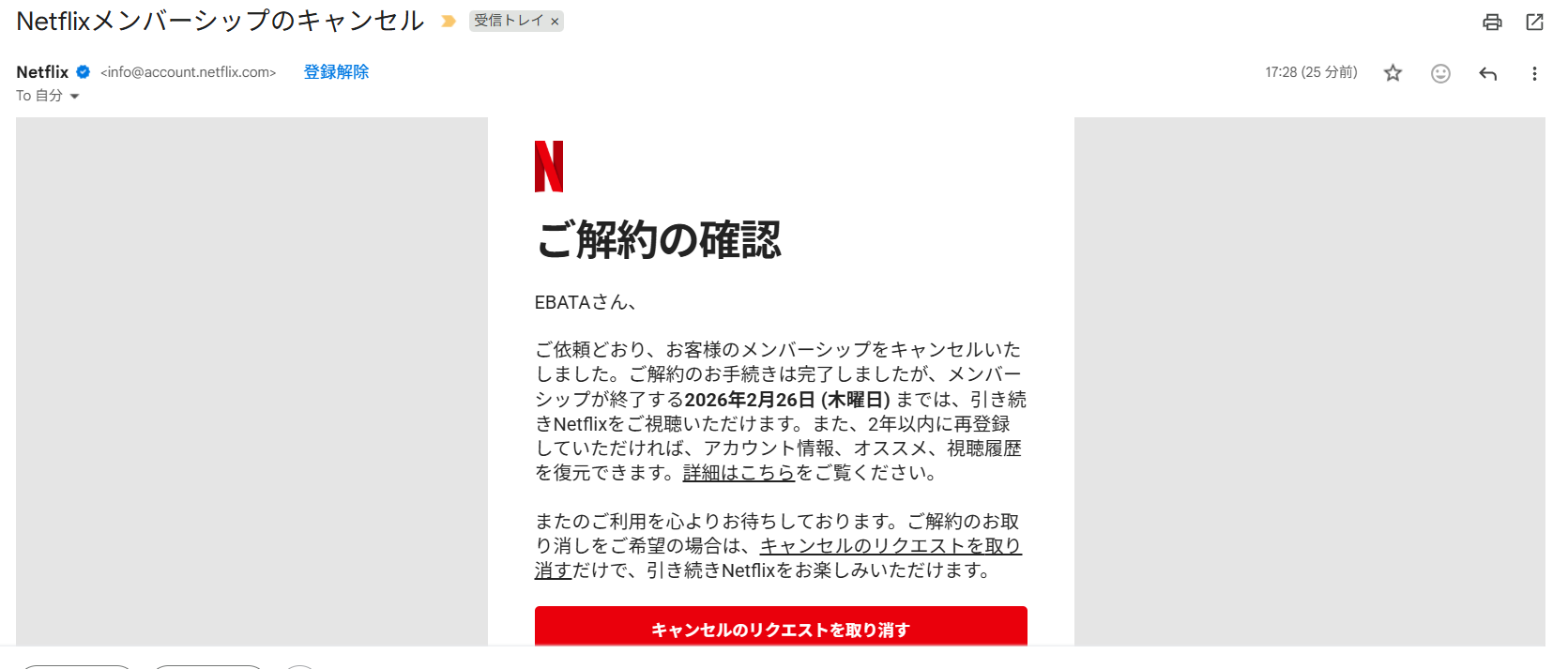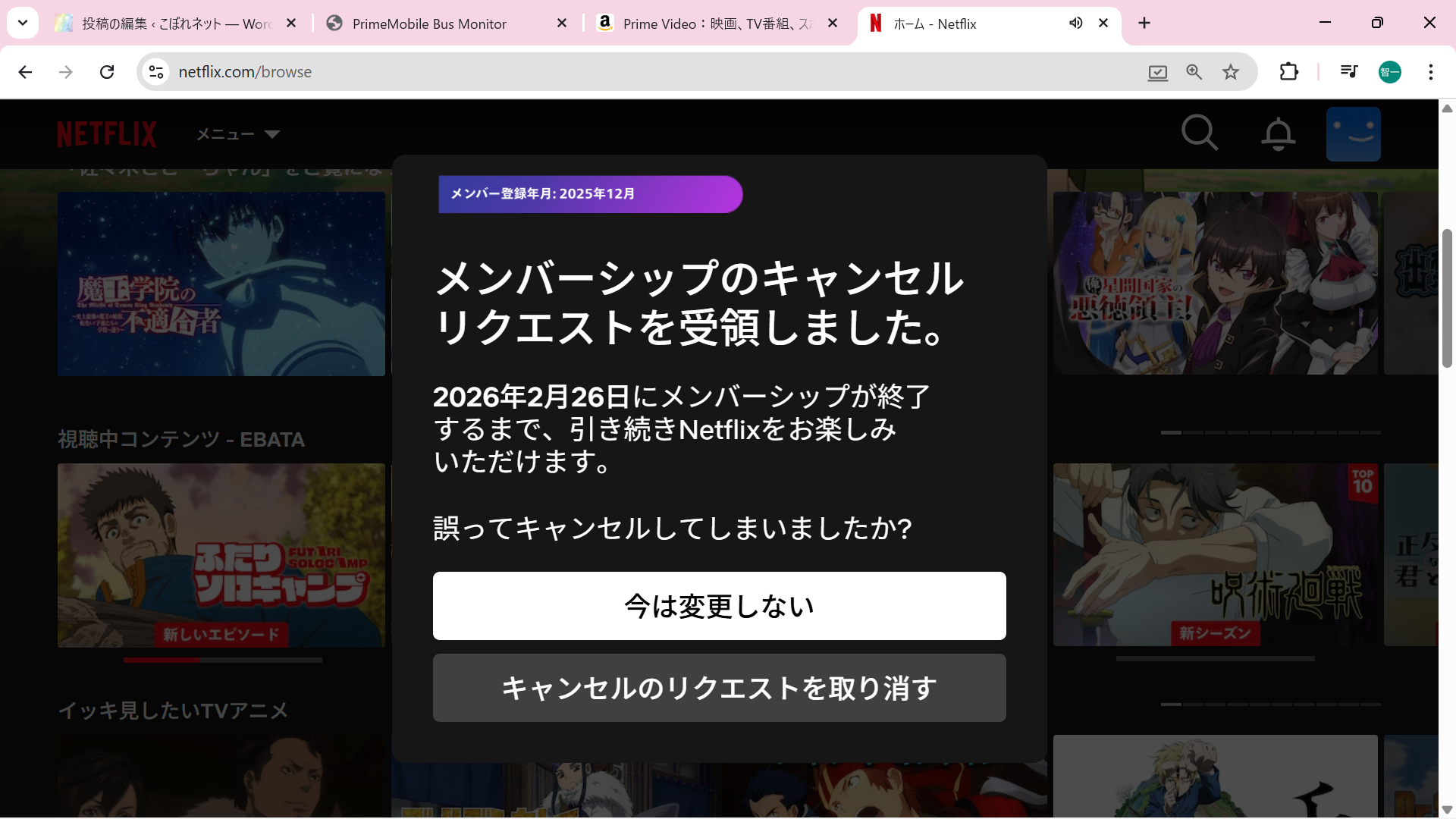以前、CEAマーカー(代表的な腫瘍マーカーの一つ)の数値について触れました。
Previously, I mentioned the value of a CEA marker, a representative tumor marker.
轢断のシバタ先生からは「再検査した方が良い」と言われ、
Dr. Shibata, who treated my crush injury, told me that I should undergo a follow-up examination.
骨折の手術を担当して下さった先生からは「CEA値と骨折には直接の関係はない」と言われ、
The doctor who handled my fracture surgery told me that there is no direct relationship between CEA values and bone fractures.
近くのクリニックの先生からは「できるだけ早く再検査を」と言われ、
A doctor at a nearby clinic advised me to get retested as soon as possible.
さらにChatGPTからは「一般的には、再検査の目安は1月下旬から2月上旬」と示された。
In addition, ChatGPT indicated that, generally speaking, the guideline for re-testing would be from late January to early February.
こうして、人と機械の双方から同じ方向の助言が重なった結果、本日、人間ドックを受けた病院を再訪し、CTスキャンと採血を受けてきました。
As a result of receiving advice pointing in the same direction from both humans and a machine, I revisited the hospital where I had undergone a medical checkup today and received a CT scan and blood tests.
そして来週、再来院するよう指示を受けました。
I was then instructed to return to the hospital next week.
正直、「面倒くさいなぁ」と思っています。
To be honest, I find it bothersome.
自覚症状はなく、これまでのレントゲン等でも異常は見つかっていません。
I have no subjective symptoms, and no abnormalities have been found in X-rays or other tests so far.
それでも、ここまで複数の主体から同じ指摘を受けている以上、「やれることはやっておくべきだ」と判断しました。
Even so, given that multiple parties have raised the same concern, I decided to do whatever could be done.
来週の再来院で何も見つからなければ、それは一つの結論になります。
If nothing is found at the follow-up visit next week, that in itself will be one conclusion.
逆に、何かが見つかったとしても、「早めに確認していた」という事実は、将来の後悔を確実に減らしてくれるはずです。
Conversely, even if something is found, the fact that it was checked early should surely reduce future regret.
少なくとも、「知らなかった」「放置していた」という状態だけは避けられます。
At the very least, I can avoid the situation of having “not known” or “left it unattended.”
―― 自分で自分を「バカ野郎」と罵る羽目になるのは、あまりに残念すぎる。
— Ending up calling myself an “idiot” would be far too regrettable.
---
最近、「セルフネグレクト」という言葉を耳にするようになりました。
Recently, I have been hearing the term “self-neglect” more often.
明確な自傷意図や希死念慮がないにもかかわらず、自身の生活・健康・安全を適切に維持できなくなる状態を指す言葉です。
It refers to a condition in which a person becomes unable to properly maintain their own life, health, and safety, despite having no clear intent of self-harm or suicidal ideation.
日本では高齢者問題や孤立問題の文脈で語られることが多いが、その本質は「怠慢」や「だらしなさ」ではありません。
In Japan, it is often discussed in the context of issues involving the elderly or social isolation, but its essence is not “laziness” or “sloppiness.”
本人は「今は大丈夫」「困っていない」「後でやればいい」と感じていることが多く、外部からの介入が遅れやすい、という特徴があります。
The person often feels that “it’s fine for now,” “there’s no problem,” or “I’ll deal with it later,” which makes external intervention likely to be delayed.
具体的には、
Specifically,
(1) 医療機関への受診を避け続ける
(1) Continuing to avoid visiting medical institutions
(2) 病気やケガを放置する
(2) Leaving illnesses or injuries untreated
(3) 食事や水分摂取が極端に偏る
(3) Extreme imbalance in diet or fluid intake
(4) 住環境が悪化する
(4) Deterioration of the living environment
(5) 周囲や公的支援を拒否する
(5) Rejecting help from others or public support
といった状態が、長期間・反復的に続きます。
These kinds of conditions continue over a long period and repeatedly.
自分自身を振り返ると、医療機関への受診もしているし、生活環境も破綻していません。
Looking back on myself, I do visit medical institutions, and my living environment has not collapsed.
この定義に照らせば、(1)から(4)には該当しないでしょう。
Judging by this definition, I would not fall under items (1) through (4).
ただし、「周囲の助言を拒否する」という点だけは、やや怪しい。
However, the point of “rejecting advice from those around me” is somewhat questionable.
もっとも、それが公的支援で、特に金銭的支援であれば話は別です。
That said, if it is public support, especially financial support, it is a different story.
その場合、私は必ず金を取りに行きます。
In that case, I will definitely go and take the money.
―― 日本国から金を取り戻すためであれば、いかなる労も厭わない
— If it is to reclaim money from the Japanese state, I will spare no effort.
この情けないまでに正直な態度を、あの野郎の言っている「アメリカ・ファースト(First)」と対比するなら、これはさしずめ「ジャパン・ワースト(Worst)」の精神と言えるでしょう。
If I were to contrast this pathetically honest attitude with that bastard’s “America First,” it could be called the spirit of “Japan Worst.”
---
今回の解散総選挙について、私は心底腹を立てています。
Regarding this snap general election, I am deeply angry.
今回の無茶苦茶な日程で、国政選挙を強制されることになったからです。
This is because we are being forced into a national election on an utterly unreasonable schedule.
私は、選挙があれば、事前に調査し、分析した上で投票に行く。
When there is an election, I conduct research and analysis beforehand and then go to vote.
―― これだけ聞けば、なかなか立派で模範的な国民です
— Hearing only that, I might seem like quite a respectable and exemplary citizen.
しかし、私は週末も働き続けています。
However, I continue working even on weekends.
本当に忙しいのです。
I am truly busy.
できれば、選挙にはあまり関わりたくない、というのが正直な気持ちです。
To be honest, if possible, I would rather not be too involved in elections.
それでも、選挙が行われる以上、真剣に向き合うのが義務だとは思っています。
Even so, as long as an election is being held, I believe it is my duty to take it seriously.
もちろん、解散権は内閣、実務上は総理大臣主導の専権的権限です。
Of course, the power of dissolution belongs to the Cabinet and is, in practice, a prerogative led by the Prime Minister.
これは否定しません。
I do not deny this.
だからこそ、その権力行使に対して、私は今回選挙権で抗議します。
That is precisely why I will protest against that exercise of power with my right to vote.
自民党の政策は――今回に限っては、一切「聞かない」。
As for the Liberal Democratic Party's policies, this time I will choose not to “listen” to them at all.
現状の政府や自民党の政策には支持できる点も多い。
There are many points in the current government’s and the LDP’s policies that I can support.
しかし、今回の「解散権の濫用」という一点だけで、私は怒っています。
However, over this single point of what I see as the “abuse of the dissolution power,” I am angry.
『あ、そう。あなたは、この重要な専権事項を、そういう使い方をするのですね。分かりました。よく分かりました。では、こちらも評価させて頂きますよ』
“Oh, I see. So this is how you choose to use such an important prerogative. I understand. I understand very well. Then, I will also proceed to evaluate you.”
そんな『狭量で矮小で、何の権力も持たない小市民の怒り』を、私が持っている選挙権(の濫用)で、たとえ私一人だけであっても、示すつもりです。
— With the right to vote that I possess, I intend to express the anger of such a narrow-minded, petty, and powerless common citizen, even if it is only me alone.
---
この一連の思考を経て、少なくとも自分は、セルフネグレクトからはまだ遠い位置にいるのではないか、という感覚が芽生えました。
After going through this chain of thoughts, I began to feel that, at the very least, I am still far from self-neglect.
自分は、
As for myself,
(1) 自分自身には期待しておらず、他人にも期待していない。
(1) I have no expectations of myself, nor of others.
(2) それでも、他人や権力が自分の思うように動かないことに対して、理不尽なまでに怒ることができる。
(2) Even so, I am able to become unreasonably angry when others or those in power do not act as I wish.
つまり、私という人間は、愛や友情によって他人や社会と接続することはできないかもしれません。
In other words, I may not be able to connect with others or with society through love or friendship.
しかし、怒りや憎しみによってであれば、他人や社会と接続していくことはできそうだ、という確信に近いものを得ました。
However, I have gained something close to a conviction that I can connect with others and society through anger and hatred.
―― 生きてやるぞ。これからも私のためではなく、私の意に沿わない権力者を邪魔するためだけに、そして国庫の出費を私のために使わせるためだけに、生きてやる。
— I will live. Not for my own sake, but solely to obstruct those in power who act against my will, and solely to make the national treasury spend money on me, I will live.
なんともネガティブで、救いのない、ダメダメな考え方です。
It is an utterly negative, hopeless, and pathetic way of thinking.
しかし―― 我が国の最高権力者が、怒りという形で、私に生きる意義を見い出させてくれた。
However, our nation’s highest authority has allowed me to find a meaning to live, in the form of anger.
その一点においてのみ、今回の「首相による解散権の濫用」を評価してやろうと思います。
In that one respect alone, I am willing to give credit to this “abuse of the dissolution power by the Prime Minister.”
―― 娘たちは無事社会人になったし、家のローンにも目途がついた。博士号も取得したし、200本程度のコラムもリリースした。仕事ではパッとしなかったかもしれんけど、まあ、良い伴侶と、楽しい家族と、比較的長い時間を過ごせた