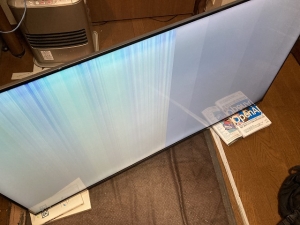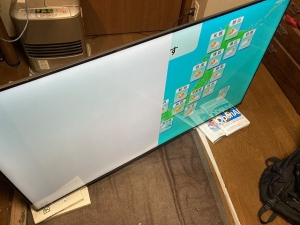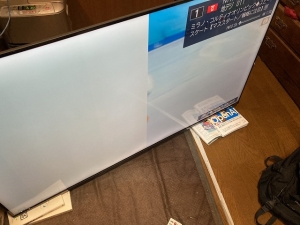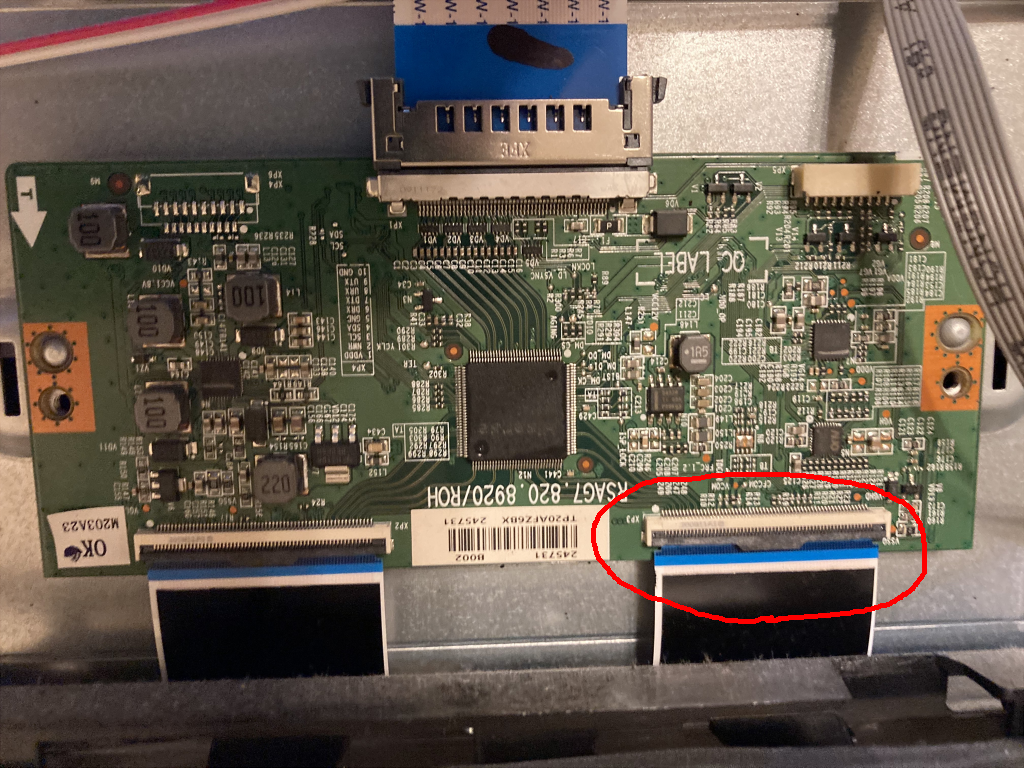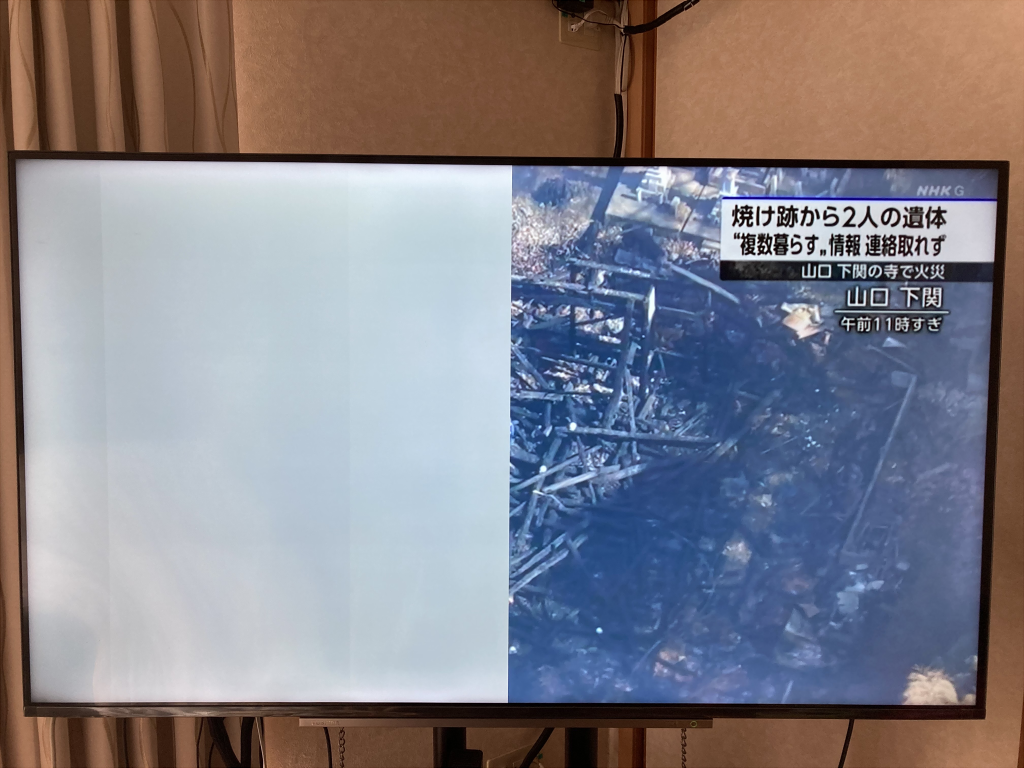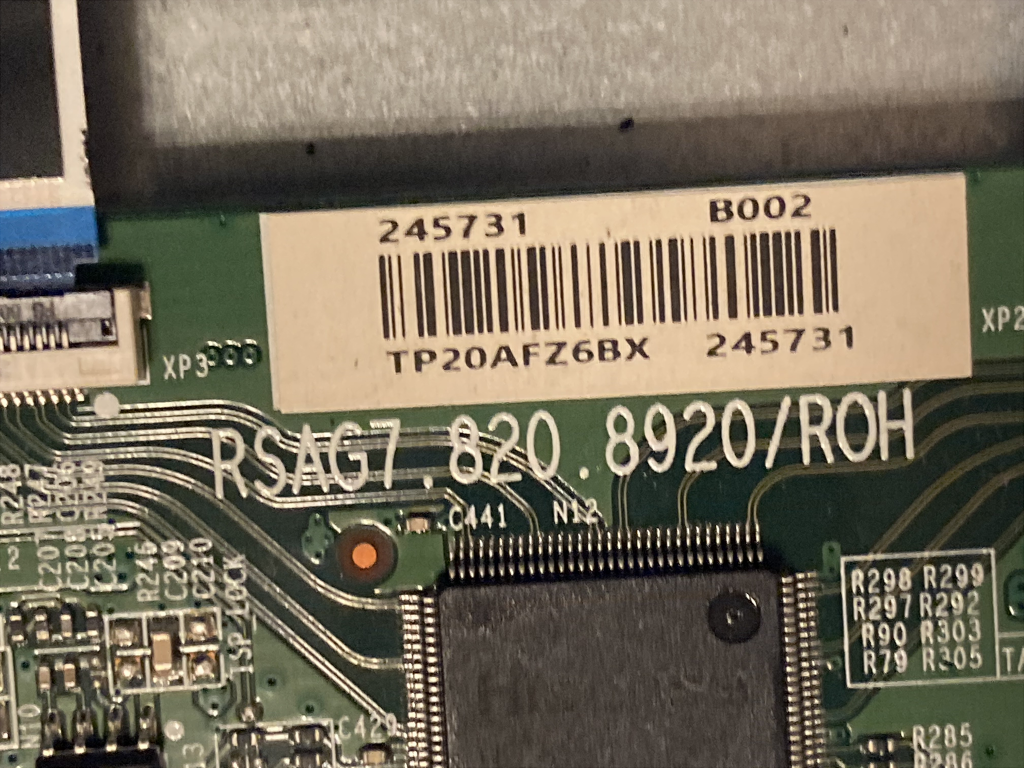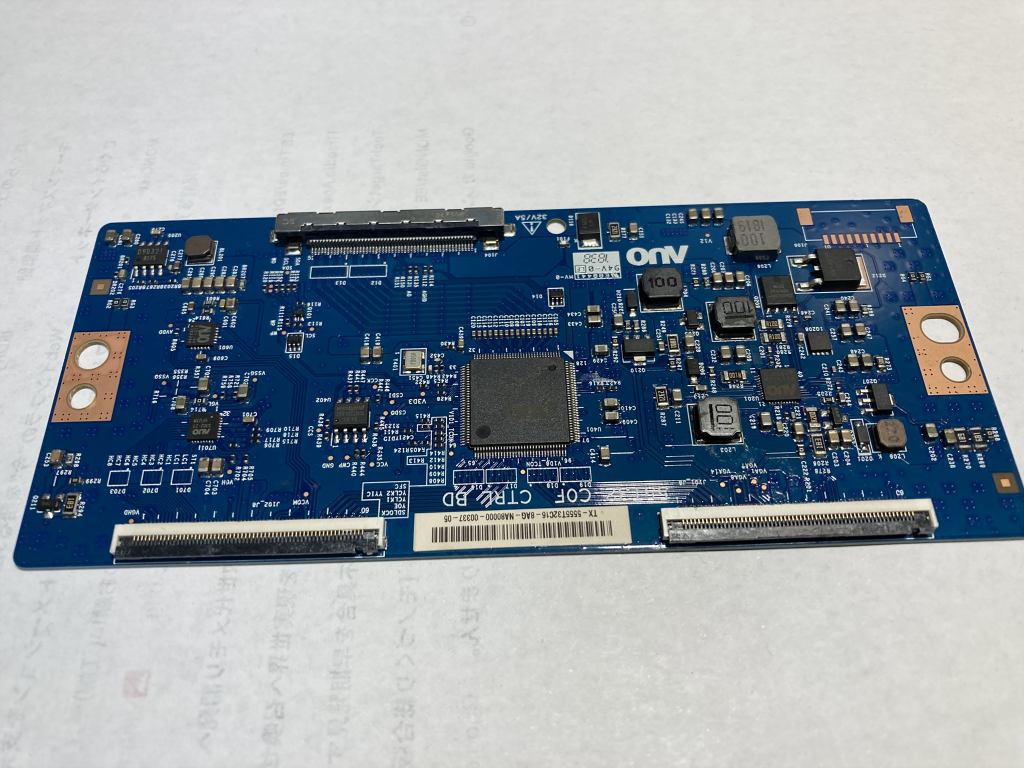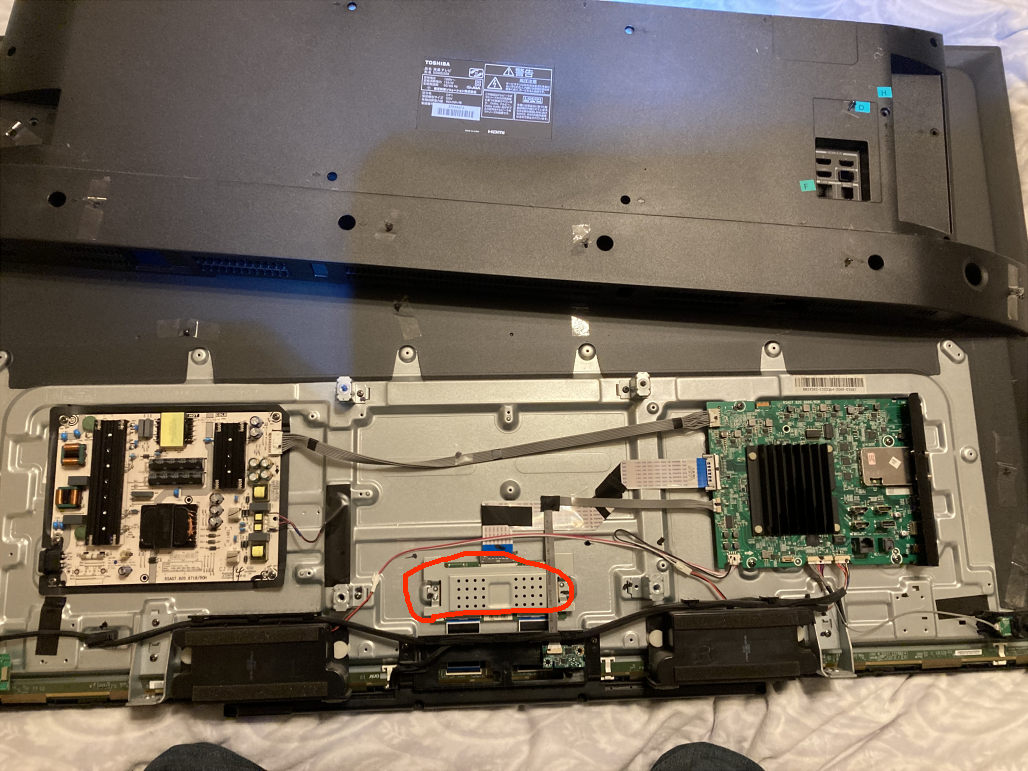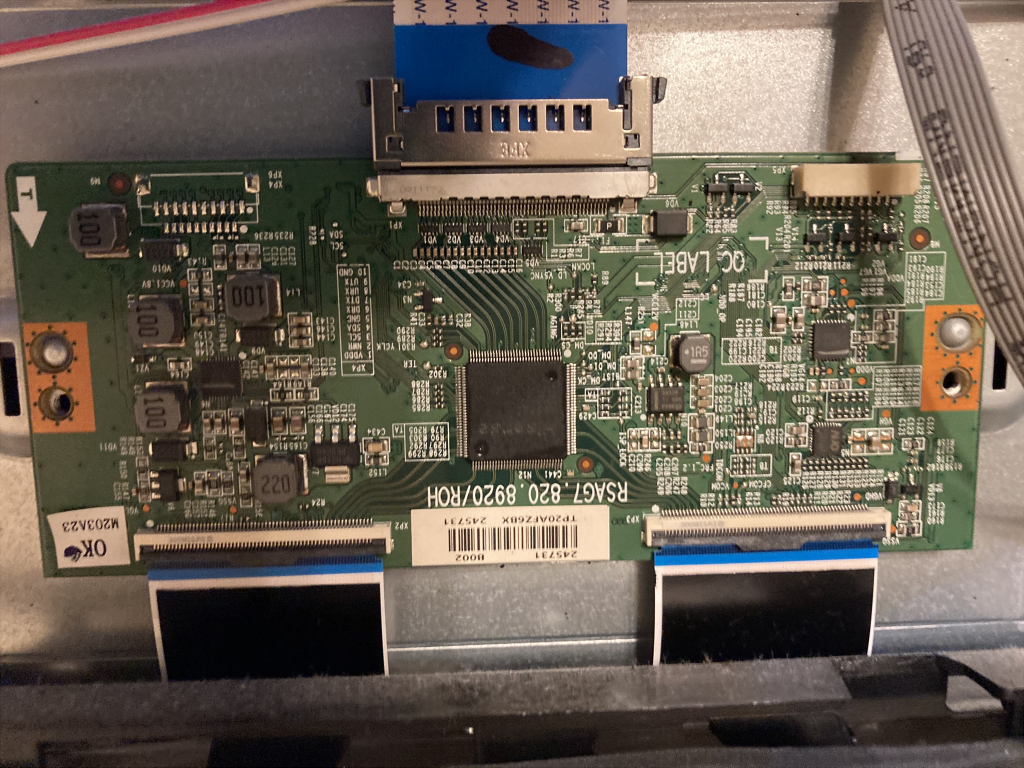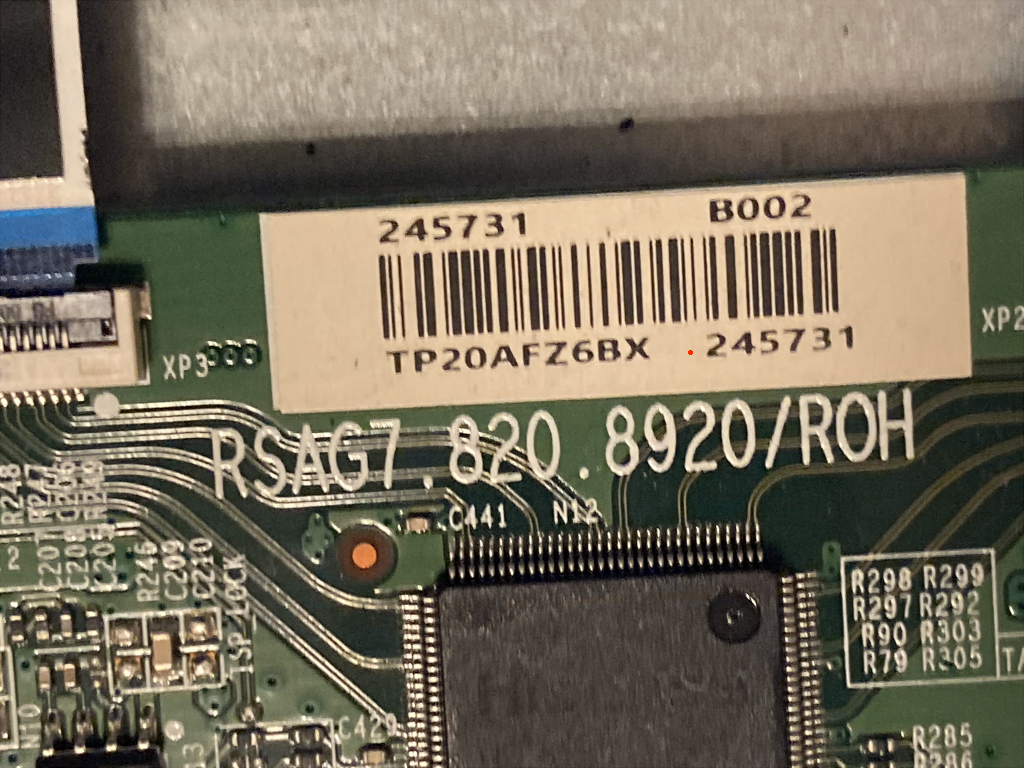https://wp.kobore.net/2025/12/10/post-23101/
HLS映像検索・サムネイル・再生システム構築手順書 - リバースプロキシ対応による公開境界分離構成HLS映像検索・サムネイル・再生システム構築手順書 - リバースプロキシ対応による公開境界分離構成.md
以下は、貼付「HLS映像検索・サムネイル・再生システム構築手順書.pdf」を前提に、**“今回の修正(= reverse-proxy 化)で追加・変更した箇所だけ”**を、**手順書内にそのまま貼り付けられる形(ファイル全文+コマンド全文)**でまとめたものです。
(方針は、貼付「映像検索・配信システム構築手順書.pdf」の reverse-proxy(Nginx)で API を隠蔽する方式を踏襲しています 。)
0. 背景と目的(今回の差分の意義)
背景
従来手順では、FastAPI が HLS(/hls)やサムネイル(/thumbs)やUI(/ui)を直接配信する構成になっており 、ブラウザからのアクセス経路が「API 直アクセス」になりがちです。また DB もホストに port 公開して運用しがちです(例:15432:5432) 。
目的(今回)
- ブラウザから見える公開点を **http://localhost/(reverse-proxy)に一本化**する
- API/DB/HLS/サムネイルを“フロントから直接見えない”(= 直接ポート露出や直配信を避ける)構造へ寄せる
- 方式は「映像検索・配信システム構築手順書.pdf」の reverse-proxy 構成(
location /api/ { proxy_pass ... }等)を踏襲
1. 今回の修正で追加するディレクトリ
既存 ~/video_hls_project の直下に、以下を 新規作成します。
cd ~/video_hls_project
mkdir -p api
mkdir -p reverse-proxy/frontend
2. 今回の修正で「新規に作る(または置き換える)」ファイル一覧
api/Dockerfile(新規)api/app.py(新規:※従来のbackend_api/app.pyを “コンテナ運用前提” にした版)reverse-proxy/Dockerfile(新規)reverse-proxy/nginx.conf(新規)reverse-proxy/frontend/index.html(新規:UIをreverse-proxy側に同梱)docker-compose.yml(置き換え)
3. ファイル全文:api/Dockerfile(新規)
作成先:
~/video_hls_project/api/Dockerfile
cat << 'EOF' > ~/video_hls_project/api/Dockerfile
FROM python:3.11-slim
WORKDIR /app
RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
build-essential libpq-dev \
&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*
RUN pip install --no-cache-dir \
fastapi uvicorn psycopg2-binary python-multipart
COPY app.py /app/app.py
EXPOSE 8000
CMD ["uvicorn", "app:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"]
EOF
4. ファイル全文:api/app.py(新規)
作成先:
~/video_hls_project/api/app.py
ポイント:
- DB内
m3u8_path(例:videos_hls/clip01/index.m3u8)を、返却URL/hls/clip01/index.m3u8に変換するロジックは従来PDFの考え方を踏襲しています /hls/thumbsを FastAPI で静的マウントする方式自体は従来PDF同様- ただし公開は reverse-proxy 経由に統一します(後述 nginx.conf)
cat << 'EOF' > ~/video_hls_project/api/app.py
from fastapi import FastAPI, HTTPException
from fastapi.staticfiles import StaticFiles
from typing import Optional
import psycopg2
import psycopg2.extras
import os
from pathlib import Path
# ========= パス設定(コンテナ内) =========
# docker-compose で /data にホストの video_hls_project をマウントする前提
BASE_DIR = Path("/data")
HLS_DIR = BASE_DIR / "videos_hls"
THUMB_DIR = BASE_DIR / "thumbnails"
# ========= DB 接続設定(コンテナ内から db サービスへ) =========
DB_HOST = os.getenv("DB_HOST", "db")
DB_PORT = int(os.getenv("DB_PORT", "5432"))
DB_NAME = os.getenv("DB_NAME", "video_db")
DB_USER = os.getenv("DB_USER", "video_user")
DB_PASS = os.getenv("DB_PASS", "password")
def get_conn():
return psycopg2.connect(
host=DB_HOST,
port=DB_PORT,
dbname=DB_NAME,
user=DB_USER,
password=DB_PASS,
)
app = FastAPI()
@app.get("/health")
def health():
return {"status": "ok"}
# ========= 静的ファイル =========
# (従来手順では FastAPI が直配信していたが、今回は reverse-proxy 経由でのみ公開する)
app.mount("/hls", StaticFiles(directory=HLS_DIR), name="hls")
app.mount("/thumbs", StaticFiles(directory=THUMB_DIR), name="thumbs")
def to_hls_url(m3u8_path: str) -> str:
"""
DBの m3u8_path (例: videos_hls/clip01/index.m3u8)
を、ブラウザ向け URL (/hls/clip01/index.m3u8) に変換する。
(従来手順書の変換仕様を踏襲)
"""
prefix = "videos_hls/"
if m3u8_path.startswith(prefix):
rel = m3u8_path[len(prefix):] # "clip01/index.m3u8"
else:
rel = m3u8_path
return f"/hls/{rel}"
def to_thumb_url(chunk_id: str) -> str:
"""
チャンク代表サムネイルは 00000.jpg を返す(従来通り)。
"""
return f"/thumbs/{chunk_id}/00000.jpg"
@app.get("/api/chunks")
def list_chunks(tag: Optional[str] = None):
"""
映像一覧API
- /api/chunks
- /api/chunks?tag=test
"""
conn = get_conn()
try:
cur = conn.cursor(cursor_factory=psycopg2.extras.RealDictCursor)
if tag:
sql = """
SELECT camera_id, chunk_id, title, m3u8_path, duration_sec, tags, created_at
FROM train_camera_chunk
WHERE tags @> ARRAY[%s]::text[]
ORDER BY id;
"""
cur.execute(sql, (tag,))
else:
sql = """
SELECT camera_id, chunk_id, title, m3u8_path, duration_sec, tags, created_at
FROM train_camera_chunk
ORDER BY id;
"""
cur.execute(sql)
rows = cur.fetchall()
result = []
for row in rows:
d = dict(row)
d["hls_url"] = to_hls_url(d["m3u8_path"])
d["thumb_url"] = to_thumb_url(d["chunk_id"])
result.append(d)
return result
finally:
conn.close()
@app.get("/api/chunks/{chunk_id}")
def get_chunk(chunk_id: str):
"""
chunk_id(clip01 等)で1件取得
"""
conn = get_conn()
try:
cur = conn.cursor(cursor_factory=psycopg2.extras.RealDictCursor)
sql = """
SELECT camera_id, chunk_id, title, m3u8_path, duration_sec, tags, created_at
FROM train_camera_chunk
WHERE chunk_id = %s;
"""
cur.execute(sql, (chunk_id,))
row = cur.fetchone()
if not row:
raise HTTPException(status_code=404, detail="chunk not found")
d = dict(row)
d["hls_url"] = to_hls_url(d["m3u8_path"])
d["thumb_url"] = to_thumb_url(d["chunk_id"])
return d
finally:
conn.close()
@app.get("/api/chunks/{chunk_id}/segments")
def get_segments(chunk_id: str):
"""
指定 chunk の index.m3u8 を読み、TSセグメント情報を返す。
(従来手順書にある /api/chunks/{chunk_id}/segments の考え方を踏襲)
"""
m3u8_path = HLS_DIR / chunk_id / "index.m3u8"
if not m3u8_path.exists():
raise HTTPException(status_code=404, detail="m3u8 not found")
segments = []
current_start = 0.0
with m3u8_path.open("r", encoding="utf-8") as f:
lines = [line.strip() for line in f if line.strip()]
i = 0
idx = 0
while i < len(lines):
line = lines[i]
if line.startswith("#EXTINF:"):
dur_part = line.split(":", 1)[1]
dur_str = dur_part.split(",", 1)[0]
try:
dur = float(dur_str)
except ValueError:
dur = 0.0
if i + 1 >= len(lines):
break
ts_name = lines[i + 1] # "00000.ts" 等
segments.append({
"index": idx,
"ts": ts_name,
"start_sec": current_start,
"duration_sec": dur,
"thumb_url": f"/thumbs/{chunk_id}/{ts_name.replace('.ts', '.jpg')}",
})
current_start += dur
idx += 1
i += 2
else:
i += 1
return segments
EOF
5. ファイル全文:reverse-proxy/Dockerfile(新規)
作成先:
~/video_hls_project/reverse-proxy/Dockerfile
(「映像検索・配信システム構築手順書.pdf」の Nginx コンテナ作り方を踏襲 )
cat << 'EOF' > ~/video_hls_project/reverse-proxy/Dockerfile
FROM nginx:alpine
COPY nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf
COPY frontend /usr/share/nginx/html
EOF
6. ファイル全文:reverse-proxy/nginx.conf(新規)
作成先:
~/video_hls_project/reverse-proxy/nginx.conf
ポイント:
/api/をapi:8000に reverse-proxy(方式は踏襲)/hls/と/thumbs/も api 側へ proxy(= ブラウザは reverse-proxy 以外に触れない)
cat << 'EOF' > ~/video_hls_project/reverse-proxy/nginx.conf
events {}
http {
server {
listen 80;
# ---- UI(静的)----
location / {
root /usr/share/nginx/html;
index index.html;
try_files $uri $uri/ /index.html;
}
# ---- API ----
location /api/ {
proxy_pass http://api:8000/;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
}
# ---- HLS(m3u8/ts)----
location /hls/ {
proxy_pass http://api:8000/hls/;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
}
# ---- Thumbnails(jpg)----
location /thumbs/ {
proxy_pass http://api:8000/thumbs/;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
}
}
}
EOF
7. ファイル全文:reverse-proxy/frontend/index.html(新規)
作成先:
~/video_hls_project/reverse-proxy/frontend/index.html
※UIは reverse-proxy 配下で配信し、API は /api/... を叩きます(踏襲の方向性:reverse-proxyで公開点を分離 )。
cat << 'EOF' > ~/video_hls_project/reverse-proxy/frontend/index.html
<!doctype html>
<html lang="ja">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" />
<title>HLS映像検索・サムネイル・再生</title>
<style>
body { font-family: sans-serif; margin: 16px; }
.row { display: flex; gap: 16px; }
.col { flex: 1; min-width: 320px; }
.grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(160px, 1fr)); gap: 10px; }
.card { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; cursor: pointer; }
.card:hover { background: #fafafa; }
img { max-width: 100%; height: auto; display: block; }
video { width: 100%; background: #000; }
.muted { color: #666; font-size: 12px; }
</style>
</head>
<body>
<h1>HLS映像検索・サムネイル・再生</h1>
<div style="margin: 8px 0;">
<label>タグ: <input id="tagInput" placeholder="例: test" /></label>
<button id="searchBtn">検索</button>
<span id="status" class="muted"></span>
</div>
<div class="row">
<div class="col">
<h2>■ サムネイル表示部(映像単位)</h2>
<div id="chunkGrid" class="grid"></div>
</div>
<div class="col">
<h2>■ セグメントサムネイル表示部(選択中の映像)</h2>
<div id="segmentGrid" class="grid"></div>
<h2 style="margin-top:16px;">■ 再生</h2>
<video id="video" controls playsinline></video>
<div id="nowPlaying" class="muted"></div>
</div>
</div>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/hls.js@latest"></script>
<script>
const statusEl = document.getElementById('status');
const chunkGrid = document.getElementById('chunkGrid');
const segmentGrid = document.getElementById('segmentGrid');
const videoEl = document.getElementById('video');
const nowPlayingEl = document.getElementById('nowPlaying');
let hls = null;
function setStatus(msg) { statusEl.textContent = msg || ''; }
async function fetchJSON(url) {
const res = await fetch(url);
if (!res.ok) throw new Error(`${res.status} ${res.statusText}`);
return await res.json();
}
function playHLS(url) {
if (hls) { hls.destroy(); hls = null; }
if (videoEl.canPlayType('application/vnd.apple.mpegurl')) {
videoEl.src = url;
} else if (window.Hls && Hls.isSupported()) {
hls = new Hls();
hls.loadSource(url);
hls.attachMedia(videoEl);
} else {
alert('このブラウザはHLS再生に対応していません(hls.jsが使えません)。');
}
}
function clearSegments() {
segmentGrid.innerHTML = '';
}
function renderChunks(chunks) {
chunkGrid.innerHTML = '';
chunks.forEach(c => {
const div = document.createElement('div');
div.className = 'card';
div.innerHTML = `
<img src="${c.thumb_url}" alt="">
<div><b>${c.title || c.chunk_id}</b></div>
<div class="muted">${c.chunk_id} / ${(c.tags||[]).join(', ')}</div>
`;
div.onclick = async () => {
setStatus(`segments取得中: ${c.chunk_id}`);
nowPlayingEl.textContent = `選択中: ${c.chunk_id}`;
clearSegments();
// セグメント一覧
const segs = await fetchJSON(`/api/chunks/${encodeURIComponent(c.chunk_id)}/segments`);
renderSegments(c.chunk_id, segs);
// 再生
playHLS(c.hls_url);
setStatus('');
};
chunkGrid.appendChild(div);
});
}
function renderSegments(chunkId, segs) {
segmentGrid.innerHTML = '';
segs.forEach(s => {
const div = document.createElement('div');
div.className = 'card';
const thumb = s.thumb_url;
div.innerHTML = `
<img src="${thumb}" alt="">
<div class="muted">#${s.index} ${s.ts}</div>
<div class="muted">${s.start_sec.toFixed(2)}s (+${s.duration_sec.toFixed(2)}s)</div>
`;
segmentGrid.appendChild(div);
});
}
async function loadChunks() {
const tag = document.getElementById('tagInput').value.trim();
const url = tag ? `/api/chunks?tag=${encodeURIComponent(tag)}` : '/api/chunks';
setStatus('chunks取得中...');
const chunks = await fetchJSON(url);
renderChunks(chunks);
clearSegments();
nowPlayingEl.textContent = '';
setStatus(`件数: ${chunks.length}`);
}
document.getElementById('searchBtn').onclick = loadChunks;
// 初期ロード
loadChunks().catch(e => {
console.error(e);
setStatus('初期ロード失敗: ' + e.message);
});
</script>
</body>
</html>
EOF
8. ファイル全文:docker-compose.yml(置き換え)
作成先:
~/video_hls_project/docker-compose.yml
ポイント:
- db / api / reverse-proxy の 3サービス化(reverse-proxy の ports 80:80 のみ公開)
- db の ports 公開は 原則やめる(必要ならコメント解除で運用)
- api は
~/video_hls_projectを/dataにマウントして HLS/サムネイルを参照する
(reverse-proxy + api + db の並びは「映像検索・配信システム構築手順書.pdf」の構成を踏襲 )
cat << 'EOF' > ~/video_hls_project/docker-compose.yml
version: "3.9"
services:
db:
image: postgis/postgis:16-3.4
container_name: train-video-db
environment:
POSTGRES_DB: video_db
POSTGRES_USER: video_user
POSTGRES_PASSWORD: password
# 重要:原則、ホストへ公開しない(フロントから見えない)
# 必要ならデバッグ時だけ一時的に開ける:
# ports:
# - "15432:5432"
volumes:
- ./db_init:/docker-entrypoint-initdb.d
- pgdata:/var/lib/postgresql/data
api:
build: ./api
container_name: train-video-api
environment:
DB_HOST: db
DB_PORT: "5432"
DB_NAME: video_db
DB_USER: video_user
DB_PASS: password
depends_on:
- db
volumes:
# ホストの ~/video_hls_project を /data として参照(HLS/サムネイルを読む)
- ./:/data:ro
# 重要:api もホストへ公開しない(reverse-proxy 経由のみ)
# ports:
# - "18000:8000"
reverse-proxy:
build: ./reverse-proxy
container_name: train-video-frontend
ports:
- "80:80"
depends_on:
- api
volumes:
pgdata:
EOF
9. 起動方法(今回版)
cd ~/video_hls_project
docker compose down
docker compose up -d --build
docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}"
期待:train-video-frontend だけが 0.0.0.0:80->80/tcp を持ち、db/api は host port を持たない。
10. 確認方法(今回版)
10.1 reverse-proxy 経由で API を確認
curl -i http://localhost/api/health
curl -i http://localhost/api/chunks
10.2 HLS の疎通確認(例:clip03)
curl -I http://localhost/hls/clip03/index.m3u8
10.3 ブラウザ確認
- Web UI:
http://localhost/ - 映像一覧(JSON):
http://localhost/api/chunks
11. 運用上の注意(今回の「フロントから見えない」化の要点)
- DBはホストへ port 公開しない(原則)
従来の15432:5432公開は、必要時のみ一時的に使う扱いに変更(元手順では公開例あり )。 - APIもホストへ port 公開しない
ブラウザはhttp://localhost/にしか触れず、/api/hls/thumbsは全て Nginx が中継。
必要なら、次に「HLS映像検索・サムネイル・再生システム構築手順書.pdf」側の **どの章・どの節に、上の差分をどう挿入するか(“差し込み位置メモ”)**も、章番号つきで作れます。