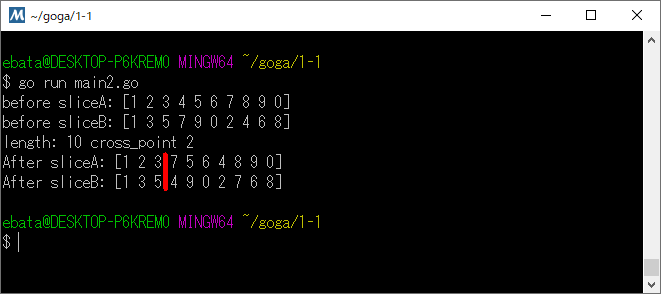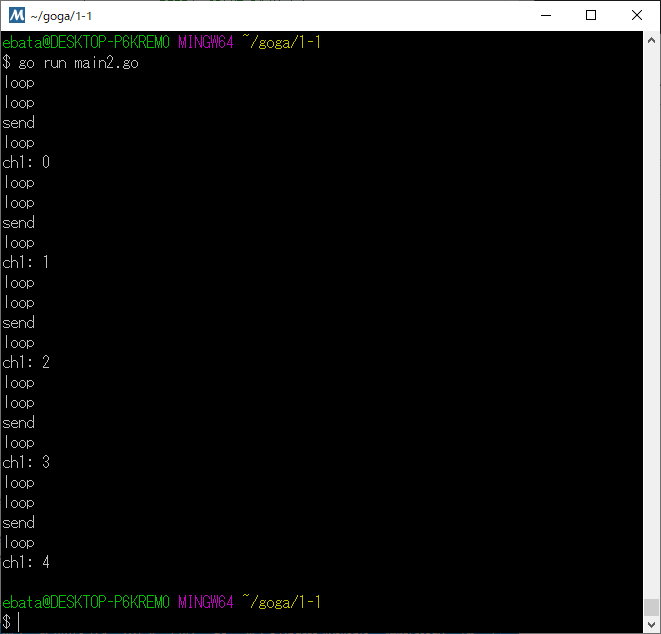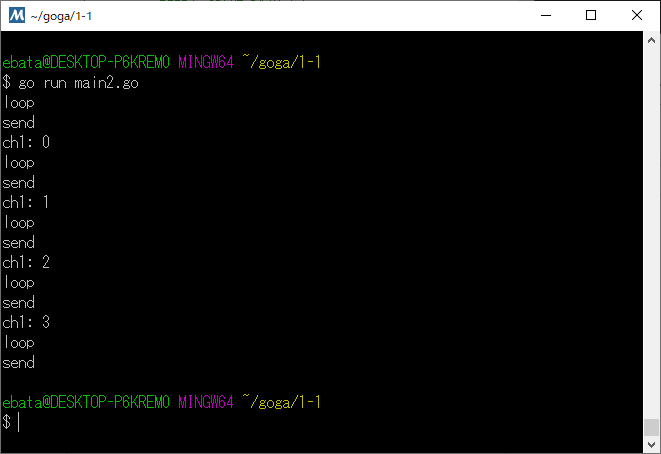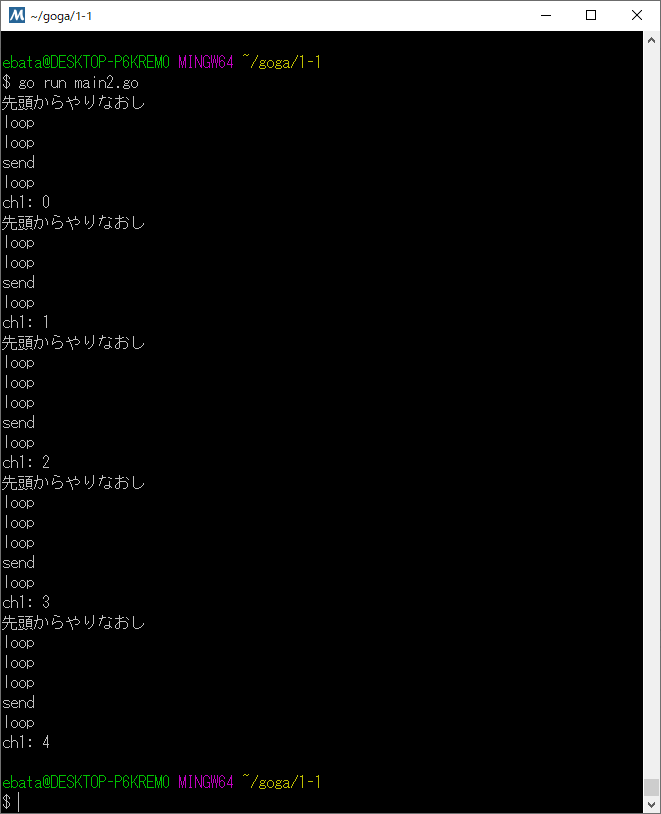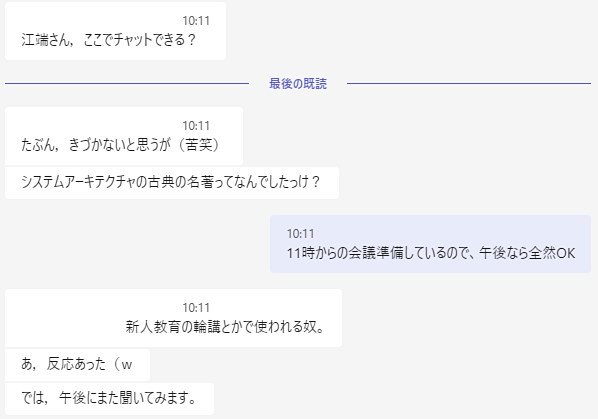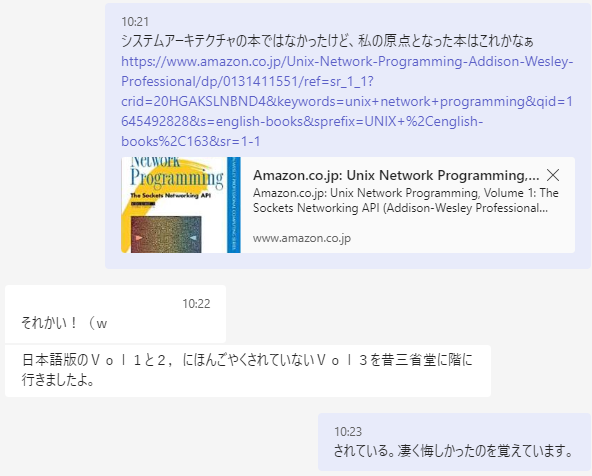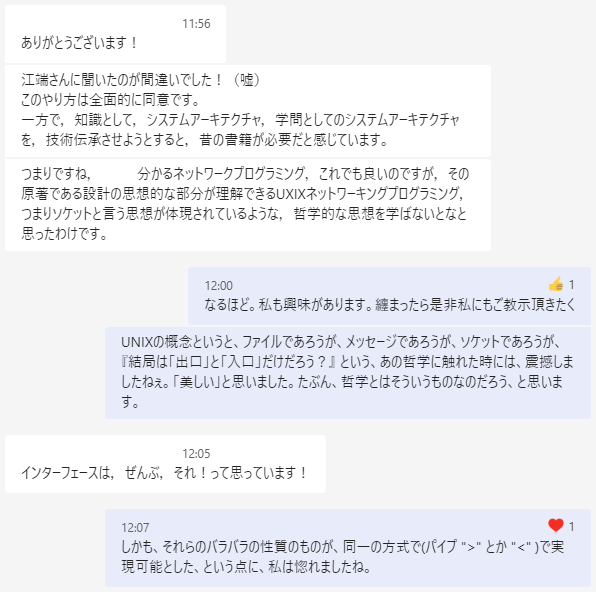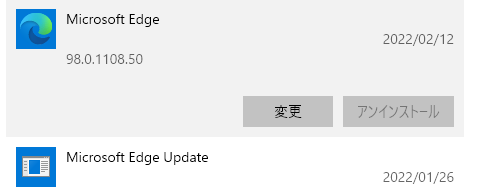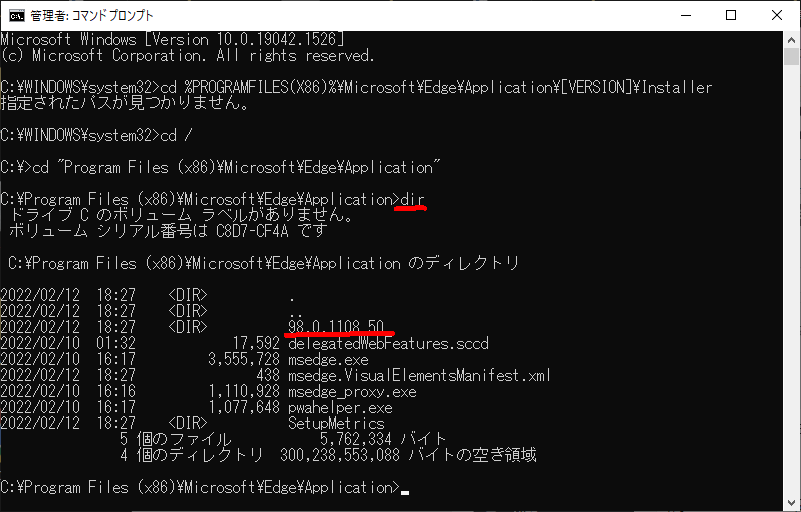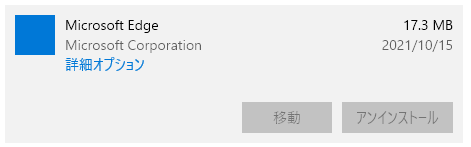以前、こちらの日記に、
という内容を掲載しました。
あの時は、会社での飲み会だったので、あまり詳しい話が聞けませんでした。
この度、私のコラムをご愛読して頂いている読者のMさんより(EE Times JapanのMさん(Ms.M)とは別の方)、詳細なレポートを頂きました。
VRを理解する上で、優れたコンテンツと思いましたので、Mさんの許諾を得て、以下に公開させて頂きます。
====== ここから =====
VRの最大の特徴は「人は視覚と聴覚を仮想されると、それを現実として認識する」です。
VRとの出会いはゲームでした。
独身一人暮らし時代、VRでバイオハザードという一人称視点のホラーゲームをプレイしていました。
プレイ中にムービーがあったんですが、その内容は
「自分が椅子に拘束され、両手首も前手で拘束された状態から、チェーンソーで両手首を切断される」
というものでした。
(自分自身もソファに座って、コントローラーを持っていたので、ムービーと全く同じ体制を取っていました)
仮想現実の自分が、両手首を切断されたとき、いの一番に自分は叫びました。
「痛ッッたくない!!!」
-----
VRでをしばらく装着すると、「ここが仮想現実である」という認識がどんどんなくなって、「仮想現実が現実化」します。
その時チェーンソーで切られた手首は間違いなく自分の手首であり、「痛くない」ことで、これがVRだったことを思い出すほどにです。
また、エースコンバットという戦闘機のフライトシミュレーションゲームのVR版をプレイした時は、ヴァーティゴに陥り、VRがなければ戦闘機パイロットでしか経験できないであろう経験をしました。
VRは現実です。
ゲームプレイ後、VRを外して見える自分の部屋を見て
「なんで俺は(洋館やコックピットでなく)ここにいるんだ?」
と一瞬思うほどには現実です。
-----
そしてVRのAVです。("ここから本論" by 江端)
先述のとおり、「VRをしばらく装着していると仮想現実が現実化」します。
僕はワクワクしながら「紗倉まなのVRAV」を購入し視聴を開始しました。
部屋の中でベッドに仰向けになっていたところ(この瞬間、僕も体勢を「座り」から「仰向け」に変えました)、部屋のドアが開き、紗倉まなが入ってきました。
自分にのしかかり、キスをしてきます。
(その際、相手の唇が少しずれるくらいなら脳が補正してくれます。)
また、立体音声でささやかれるのも、主観視点もあいまって「紗倉まながそこにいる」と錯覚させるものに十分なものでした。
しかし、ついに紗倉まなが自分のズボンを下ろしたとき、その光景のせいで、途端に自分の脳が仮想現実であることを認識してしまいました。
「俺の脚じゃない」
ズボンを脱がされて出て来た(VR上の)自分の脚が、(実際の)自分の脚より細く、一気に仮想現実であることを突きつけられました。
その後パンツを脱がされたあと、もちろんモザイクが入ってましたが、正直、脚の細さで冷静になれていましたので、そこで特にショックはありませんでした。
-----
その後自分がVRAVを購入する際に気をつけていた点は2つです。
・ズボンを脱がされない(主観側がチャックを下ろすのみの露出)
・陰茎が「模型」(男優の陰茎ではなく陰茎の模型であることにより、抽象度が増すことで脳が騙されやすい)
-----
今は妻もいますので、VRAVを利用することは全くなくなりました(VRを装着したまま自慰行為に励む姿を絶対に妻に見られたくない)が、
―― あれは、自分にとって、エロのパラダイムシフトでした。
====== ここまで =====
以上、非常に秀逸なレポートを、ありがとうございました。