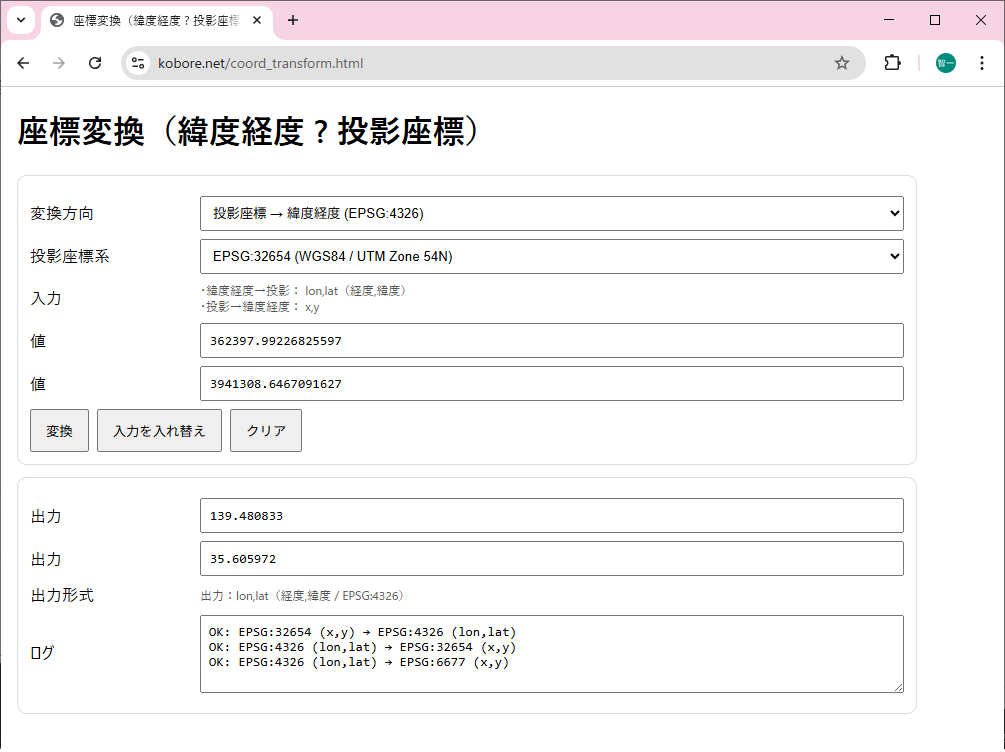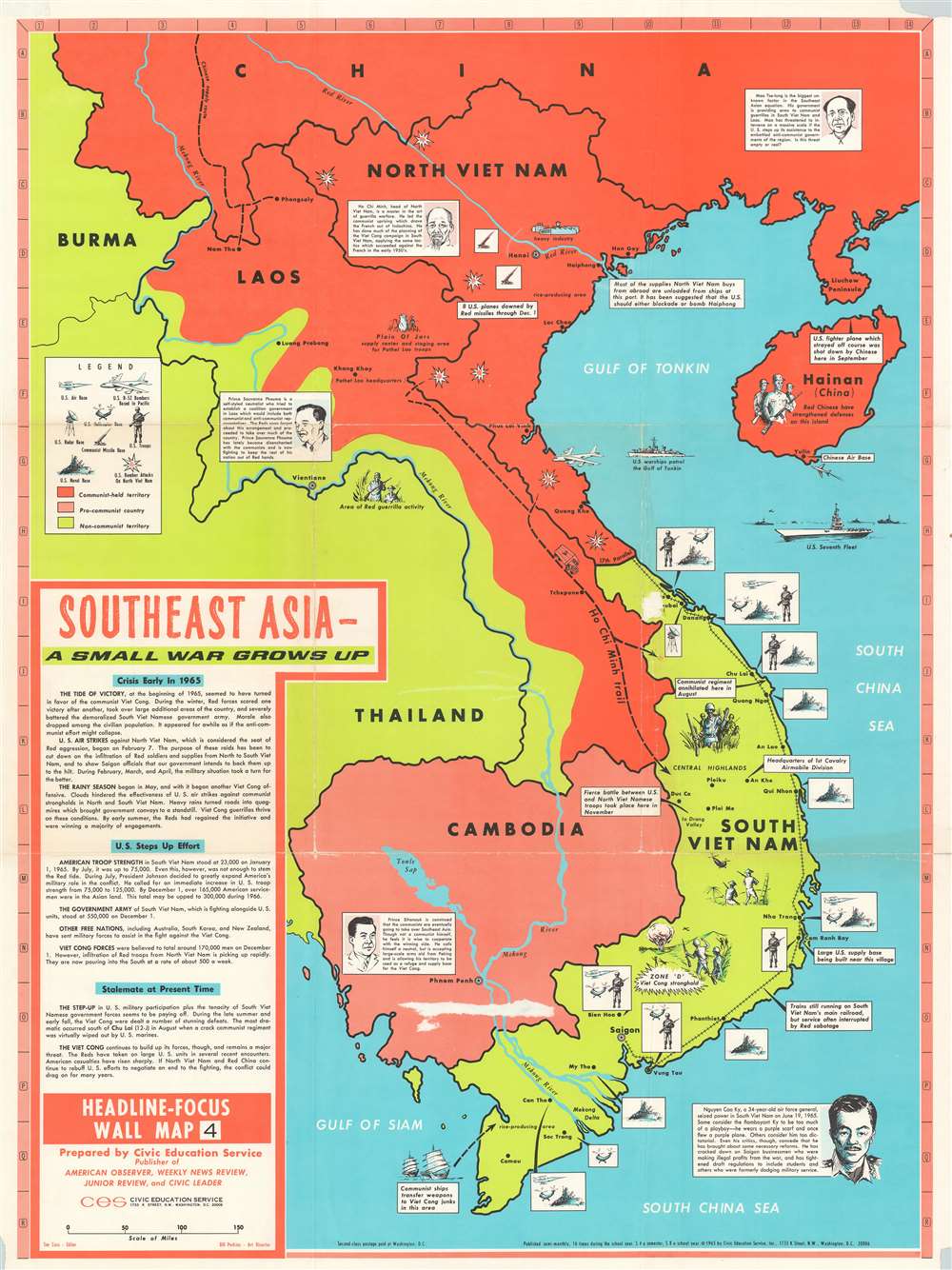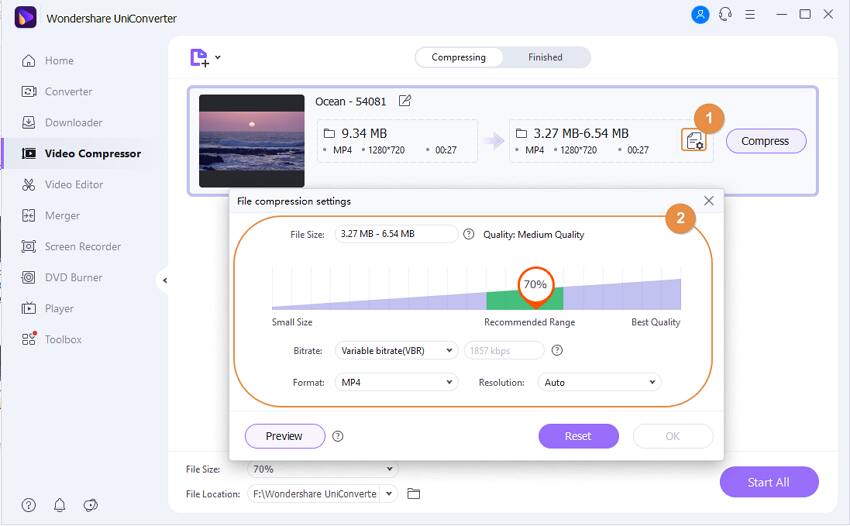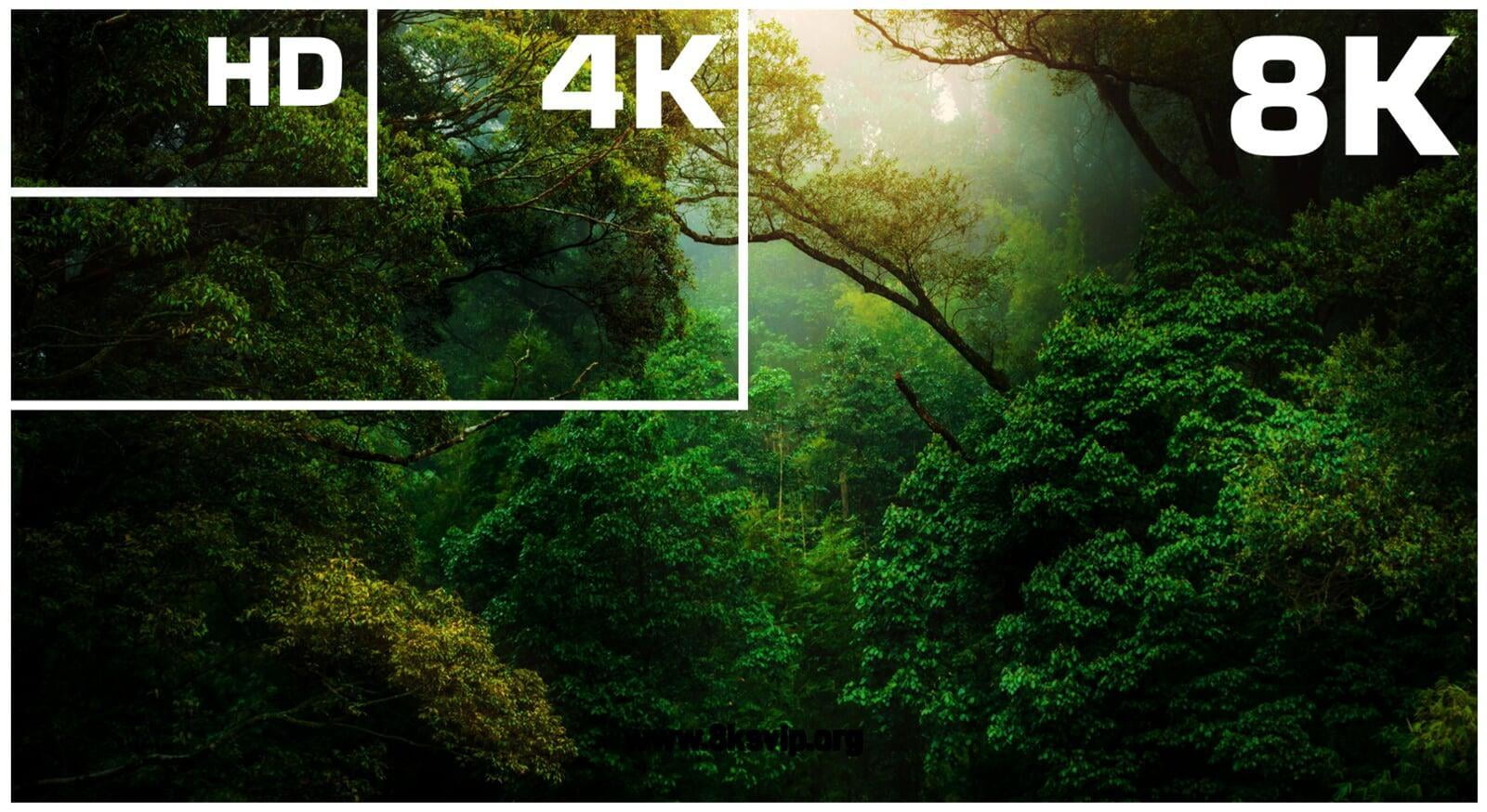昨日の日曜日、嫁さんと二人で、2km先にある市民センターまで「期日前投票」をしに、歩いて行ってきました。
Yesterday, my wife and I walked together to the civic center, 2 kilometers away, to cast an early vote.
以前にも、同じように歩いて行って「今日はやっていません」と言われたことがあり、正直、嫌な予感はしていました。
I had once walked there in the same way before, only to be told, "It’s not being held today," so to be honest, I had a bad feeling this time as well.
それでも今回は、
Even so, this time,
(1) 最高裁判官国民審査が2月1日から可能になる
(1) The Supreme Court justice review would be possible starting February 1,
(2) 投票日まで1週間もない状況で、期日前投票をやっていないわけがない
(2) and with less than a week remaining before election day, there was no way early voting wouldn’t be available,
と考え、「さすがに今回は大丈夫だろう」と判断しました。
So I thought, "Surely this time it will be fine," and made my decision.
---
結果、市民センターの入口には、
As a result, at the entrance of the civic center,
「期日前投票は2月3日(火)からです」
"Early voting starts on Tuesday, February 3."
という紙が、これ以上ないほど静かに貼ってありました。
was written on a piece of paper and posted with an almost unsettling calm.
もちろん、事前に確認もしなかった私が悪いです。そこは否定しません。全面的に私のミスです。
Of course, it was my fault for not checking in advance. I don’t deny that at all. It was entirely my mistake.
しかし、それを差し引いても、どうしても納得できない。
But even after accounting for that, there is something I cannot accept.
―― 期日前投票が、投票直前の休日にできないって、何なんでしょうか。
"What does it mean that early voting isn’t available on the weekend just before election day?"
平日は仕事で動けない。
On weekdays, I can’t move because of work.
投票日はすでに予定が入っている。
On election day, I already have plans.
だからこそ「期日前投票」という制度があるはずです。
That is precisely why an "early voting" system exists.
にもかかわらず、その期日前投票が、休日に使えない。
And yet, early voting cannot be used on a weekend.
これは単なる「不便」ではありません。
This is not a mere inconvenience.
『制度として、結果的に投票を妨げている』としか思えません。
I can only see it as a system that, in effect, obstructs voting.
さらに、今回は最高裁判官国民審査があります。
Moreover, this election includes a review of the Supreme Court justices.
これは2月1日以降でなければ行使できません。
This cannot be exercised until February 1.
結果として私は、
As a result, I was pushed into the following situation:
- 休日(先週の週末)は使えなかった
- I couldn’t use the weekend (last weekend),
- 平日には行けない(定時後も仕事がある)
- I can’t go on weekdays (my work schedule is packed),
- 投票日当日には予定がある
- and I have plans on election day itself.
という状況に追い込まれました。
That is the situation I was forced into.
―― 投票したくても、投票ができない。
"Even though I want to vote, I cannot vote."
これは、どう言い繕っても、『事実上の選挙(投票)妨害』です。
No matter how you dress it up, this is effectively an inability to exercise my right to vote.
---
念のために言っておきますが、今回の選挙日程が「違法」だとは言いません。
To be clear, I am not saying that this election schedule is illegal.
法律上は、問題ありません。
Legally, there is no problem.
衆議院解散の根拠は、日本国憲法第7条にあります。
The basis for dissolving the House of Representatives is Article 7 of Japan's Constitution.
「天皇は、内閣の助言と承認により、国事行為として衆議院を解散する」
"The Emperor, with the advice and approval of the Cabinet, shall dissolve the House of Representatives as an act of state."
実務上は、内閣(=首相)が事実上の裁量で解散時期を決められる、という運用が確立しています。
In practice, an established convention allows the Cabinet (that is, the Prime Minister) to decide the timing of dissolution at its own discretion.
ここには、「○日前に予告せよ」や「国民生活への配慮義務」といった条文上の制約はありません。
There are no statutory constraints such as "advance notice X days beforehand" or "an obligation to consider citizens’ daily lives."
だから、この選挙そのものに違法性はないのです。
That is why there is no illegality in this election itself.
では、やろうと思えば「解散の次の日に選挙」ができるのかというと、これもできません。
Then, if one really wanted to, could an election be held the day after dissolution? The answer is no.
公職選挙法によれば、最低でも12日は必要とされているからです。
According to the Public Offices Election Act, a minimum of 12 days is required.
つまり、
In other words,
『法律上は、解散の翌日に選挙はできないが、生活者が対応できないほど短い日程は、合法的に設定できる』
"Legally, an election cannot be held the day after dissolution, but a schedule so short that ordinary people cannot cope with it can still be set lawfully."
ということになります。
That is what this means.
[データ]
[Data]
- 今回の選挙戦期間(公示→投票)は、過去の例と比べてかなり短く、制度上の最短限界です。
- The campaign period in this election (from official announcement to voting day) is significantly shorter than in past cases and is set at the minimum limit allowed by the system.
- 従来の平均値は約18~20日間程度で、今回の12日間はそれより6~8日(約1週間)短いです。
- The conventional average is approximately 18 to 20 days, meaning that the current 12-day period is 6 to 8 days (about one week) shorter than usual.
---
しかし、私は声を大にして言いたい。
However, I want to say this loudly and clearly.
―― 合法であれば、何をやってもいいのか
"If it is legal, does that mean anything goes?"
この日程設定は、首相の解散権という、極めて強力な権限を使って、「投票できない人が出ることを、結果として許容する形で」行われたものです。
This scheduling was carried out by exercising the Prime Minister’s compelling authority to dissolve the Diet, in a way that ultimately tolerates the emergence of people who cannot vote.
それを私は、『解散権の濫用』と呼ばずに、何と呼べばいいのか分かりません。
Can I not see this as anything other than an abuse of the power of dissolution? I don’t know what else to call it.
行政の現場を責める気はありません。彼らは、決められた日程に従って業務をしているだけです。
I have no intention of blaming those working on the administrative front lines. They are simply carrying out their duties calmly according to the set schedule.
問題は、この日程を選び、その結果として国民の一部が投票からこぼれ落ちることを、『解散権の行使者が"無視"したことそのもの』です。
The problem lies with those who chose this schedule and who do not consider it a problem that, as a result, a portion of the electorate is excluded from voting.
私は今回、棄権します。というより、『棄権せざるを得ません』。
This time, I will abstain from voting. Or rather, "I am forced to abstain.2
投票したくないからではありません。政治に興味がないからでもありません。『投票できないようにされた』からです。
It is not because I do not want to vote. Nor is it because I am uninterested in politics. It is because I was made unable to vote.
---
それにしても ――
Even so,
『このことに、心底腹を立てているのは、私だけ』なのでしょうか。
Am I really the only one who is angry?