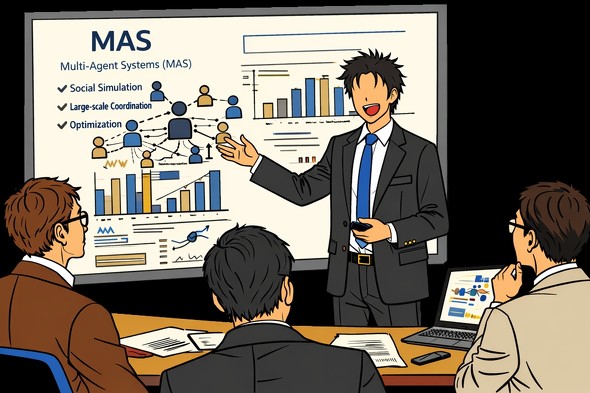新しく上司になった人間は、新しいことを始めたがります。
People who have just become supervisors tend to start new initiatives.
それは、組織を良くしようという善意からであることが多いのですが、現場にとっては必ずしも福音ではありません。
This is often driven by good intentions to improve the organization, but it is not necessarily a blessing for those on the front lines.
なぜなら、新しく導入される「やり方」は、多くの場合、上司にとって良いやりかたではあっても、部下にとっては面倒なことが多いからです。
Because newly introduced "ways of doing things" may be beneficial for the supervisor, but they are often troublesome for subordinates.
「新しく導入される"やり方"」は、良いこともあります。しかし、これは善し悪しの問題ではありません。
These "newly introduced methods" may sometimes be good. However, this is not a matter of good or bad.
しかし、その変更に付き合わされる現場は、手順の再学習、運用の調整、想定外のトラブル対応など、多大な負荷を背負うことになります。
However, the people on the ground who must adapt to these changes end up bearing a heavy burden relearning procedures, adjusting operations, and handling unexpected troubles.
要するに、
In short,
―― 面倒くせい
"it's a hassle."
です。
That's what it comes down to.
---
「改革」というのが、多くの場合上手くいかないのは、大きく2つ理由があります
There are broadly two reasons why "reforms" often fail.
(1)「改革」は、成功するか失敗するか分からない。先例がないから。
(1) A reform may succeed or fail; there is no precedent.
(2)成功するか失敗するか、どちらにせよ、新しいことを強いられるのは面倒で不愉快だから
(2) Whether it succeeds or fails, being forced into something new is troublesome and unpleasant.
既存の方式が、それなりに機能しているのであれば、わざわざ「改革」なんぞ望みません。
If the existing system is functioning reasonably well, no one goes out of their way to seek reform.
「改革」は誰のためにあるのか ーー 畢竟(ひっきょう)、「改革を試してみたい人のため」"だけ"にあります。
For whom does reform exist? Ultimately, it exists only for those who want to try reform.
加えて、もう一つ理由を加えるのであれば、
If one more reason were to be added,
(3)「改革」が成功したとしても、それが大きく評価されることは極めてまれである。その「改革」は、後発的に『誰がやっても同じだった』として、歴史の中に埋没されていくから
(3) Even if a reform succeeds, it is rarely highly valued; it later gets buried in history as something "anyone could have done."
もあるでしょう。
That too may be the case.
いわゆる、「コロンブスの卵」というやつです。これは、改革を目指す人にとっても、負の動機(改革を実施しない言い訳)になると思います。
This is what is called the "Columbus's egg." It can even become a negative motivator, an excuse not to implement reform.
---
冒頭に上げた事例も含めて、こうした営みは「政治改革」です。
Including the example mentioned at the beginning, such efforts are "political reform."
政治とは、別に国会や行政で行われているものだけでなく、会社の部や課のレベルは勿論、家族や、友人間でも行われるものであり、そして、多くの場合「政治改革」は、
Politics is not only what happens in parliament or government; it takes place within company departments, families, and among friends, and in many cases, "political reform":
(1)実施されない
(1) Is never implemented,
(2)実施されて、失敗する
(2) Is implemented and fails,
(3)実施されて、成功して、すぐに忘れ去られる
(3) Is implemented, succeeds, and is quickly forgotten.
の3つの運命しかありません。
These are the only three possible outcomes.
以上、「政治改革の被害者」と「政治改革の実施者」の両方の視点からの分析をしてきました。
Thus far, this has been an analysis from both the victim's and the implementer's perspectives of political reform.
---
私も若いころは、自分の能力の範囲での「政治改革の実施者」をやってきたつもりです。それが、家庭内であったり、テニスサークルであったり、自分の課の中であったりと ーー 随分とチンケなレベルではありますが。
When I was younger, I too considered myself an implementer of "political reform" within my limited capacity, whether at home, in a tennis club, or within my department, though admittedly at a rather trivial level.
ただ、歳を経ることによって、上記の「政治改革」の3つの背景と3つのアウトプットを感じるようになってきて、いつしか『改革者側に立つのは、面倒くさい』と思うようになってきました。
However, as I grew older, I began to sense the three backgrounds and three outcomes of such "political reform," and gradually came to feel that standing on the reformer's side was simply a hassle.
この『面倒くさい』が最高レベルに達した時に、私が至った一のパラダイムが、
When this sense of hassle reached its peak, I arrived at a paradigm:
―― たった一人の政治改革
"political reform by just one person."
です。
That was it.
---
たとえば、私が課内の「政治改革の実施者」であった頃の話です。
For example, when I was acting as a reformer within my department:
ある時、私は、「会議が多すぎる」という、誰もが一度は思う問題に直面しました。
At one point, I faced the common complaint: "There are too many meetings."
週次会議、進捗会議、レビュー会議、報告会議 ーー 名称は違いますが、要するに全部同じです。
Weekly meetings, progress meetings, review meetings, reporting meetings, different names, but essentially the same.
私は、これを改革しようとしました。
I tried to reform this.
まず、(1)会議時間の半減、(2)事前資料の提出義務化、(3)発言者の事前登録、(4)決定事項の即時ログ化、という、『効率化された新会議制度』を設計しました。
First, I designed an "efficient new meeting system": (1) halving meeting time, (2) mandatory pre-submission of materials, (3) pre-registration of speakers, and (4) immediate logging of decisions.
資料を作り、関係者に説明し、導入しました ―― 結果、『会議は半減しませんでした』。
I prepared materials, explained them to stakeholders, and implemented the results: meetings were not halved.
事前資料は提出されず、発言者登録は形骸化し、ログは誰も見ませんでした。
Materials were not submitted, speaker registration became a formality, and no one looked at the logs.
そして何より、『新しい運用ルールの説明のための会議』が追加されました。
Above all, a "meeting to explain the new rules" was added.
つまり、私は「会議を減らす改革」によって、『会議を増やした』のです。
In short, through a reform meant to reduce meetings, I increased them.
―― うん、バカとしか言いようがない
"Yes, there's no way to describe it except as foolish."
"反省"や"自己批判"という言葉を越えて「呆れて笑うしかない」 ―― "自嘲自棄(じちょうじき)"です。
Beyond "reflection" or "self-criticism," it left me only able to laugh in exasperated self-mocking despair.
---
その後の私は、一切の会議改革を提案することをやめました。
After that, I stopped proposing any reforms to meetings.
その代わり、自分の出席する会議だけ、「本当に必要なこと以外は発言しない」という運用を開始しました。
Instead, I began operating under a rule in meetings I attended: not to speak unless necessary.
(正確にいうと『議論の発散を防ぎ、収束する方向に姑息に誘導する』運用ですが)
(More precisely, I subtly steered discussions to prevent divergence and move toward closure.)
驚くべきことに、私が発言しなくても、会議は進行し、決定もなされ、議事録も問題なく作られました。
Remarkably, even without my speaking, meetings proceeded, decisions were made, and minutes were created without issue.
何一つ問題は起きませんでした。それどころか、会議時間は短縮されました。
No problems arose; in fact, meeting times were shortened.
私が、説明や補足は新規な事項を言い出さないように努めた結果、議論が拡散しなかったのです(議論を「発展させなかった」とも言えますが)。
By refraining from introducing new points in explanations or clarifications, discussions did not spread outward (or one could say they did not "develop").
私は、会議制度を変えなかったにも関わらず、会議の運用を変えてしまったのです ―― 私の主催する会議についてだけ、ですが。
Without changing the meeting system, I had changed its operation at least for the meetings I chaired.
---
その後、「江端さんは、会議を時間以内にきっきりまとめる」という評価を受けるようになったという話も聞きましたが、私は何もしていません。
Later, I heard that I was evaluated as someone who neatly wraps up meetings within the allotted time, but I did nothing.
本当に「何もしなかった」。
Truly, I did nothing.
制度を変えるのではなく、改革者を一人減らす ―― その改革者が、たまたま私だった、というだけの話です。
Rather than changing the system, I reduced the number of reformers by one; that reformer just happened to be me.
---
改革を否定する改革 ―― これが、私の至った「たった一人の政治改革」です。
A reform that denies reform, that is, the "political reform by just one person," I arrived at.
『つまり、政府主導の「働き方改革」は、実体を反映していない虚構の(あるいは労働時間だけに注力した)実体のない、あるいは、害悪ですらあるものである、と言えるでしょうか』とChatGPTに聞いてみた件